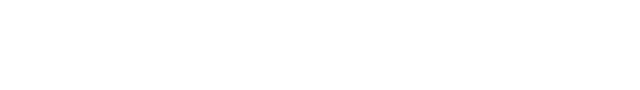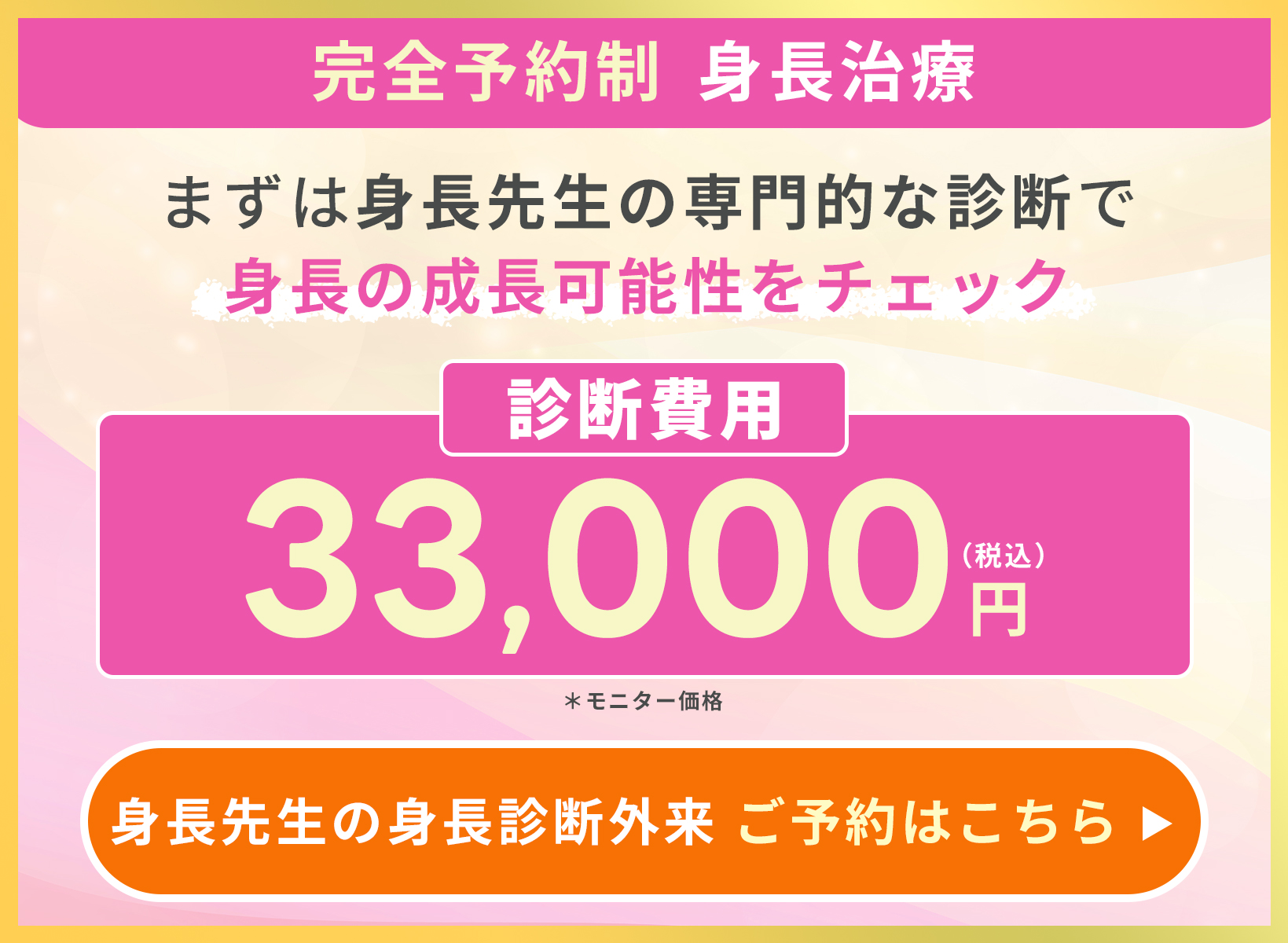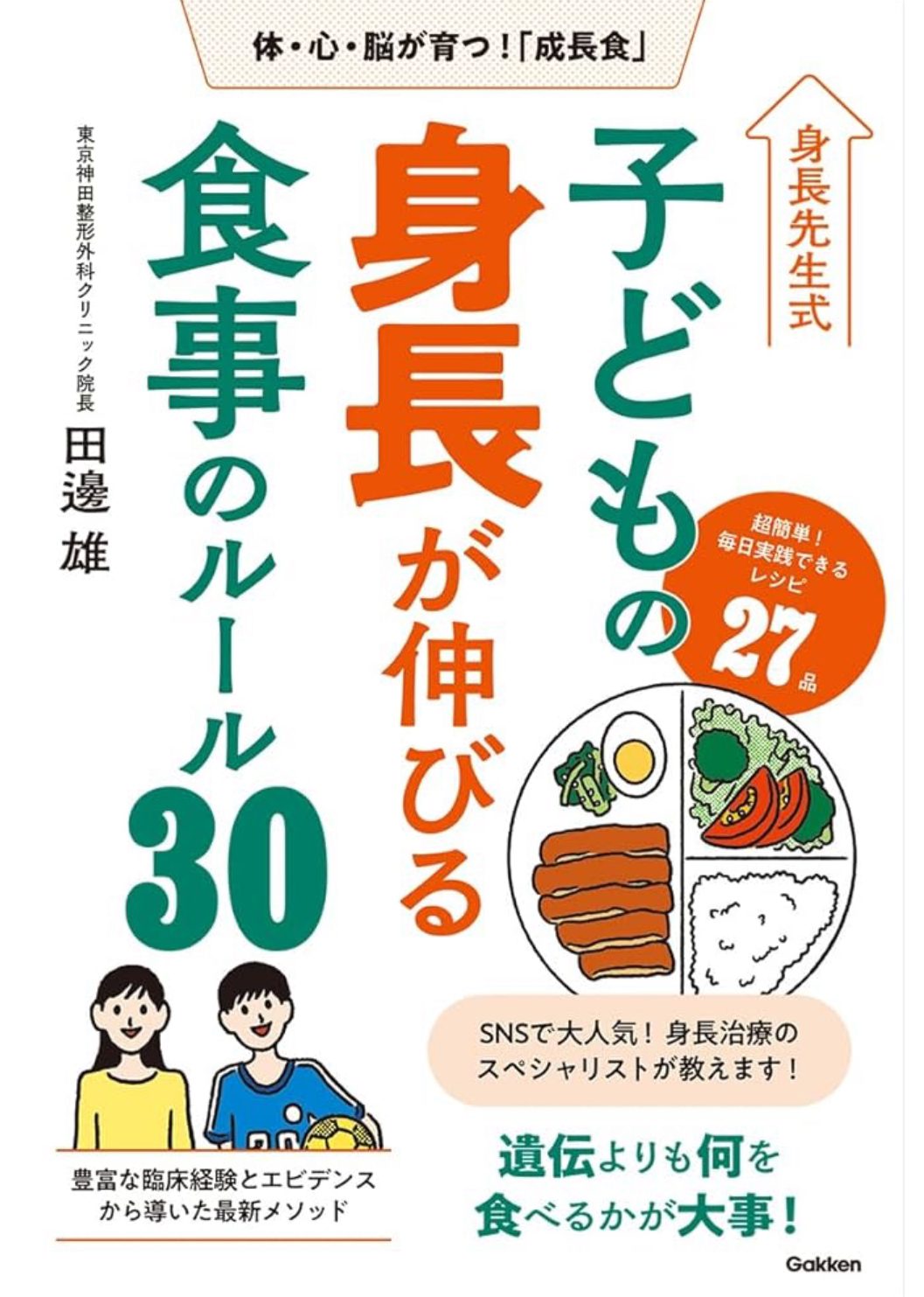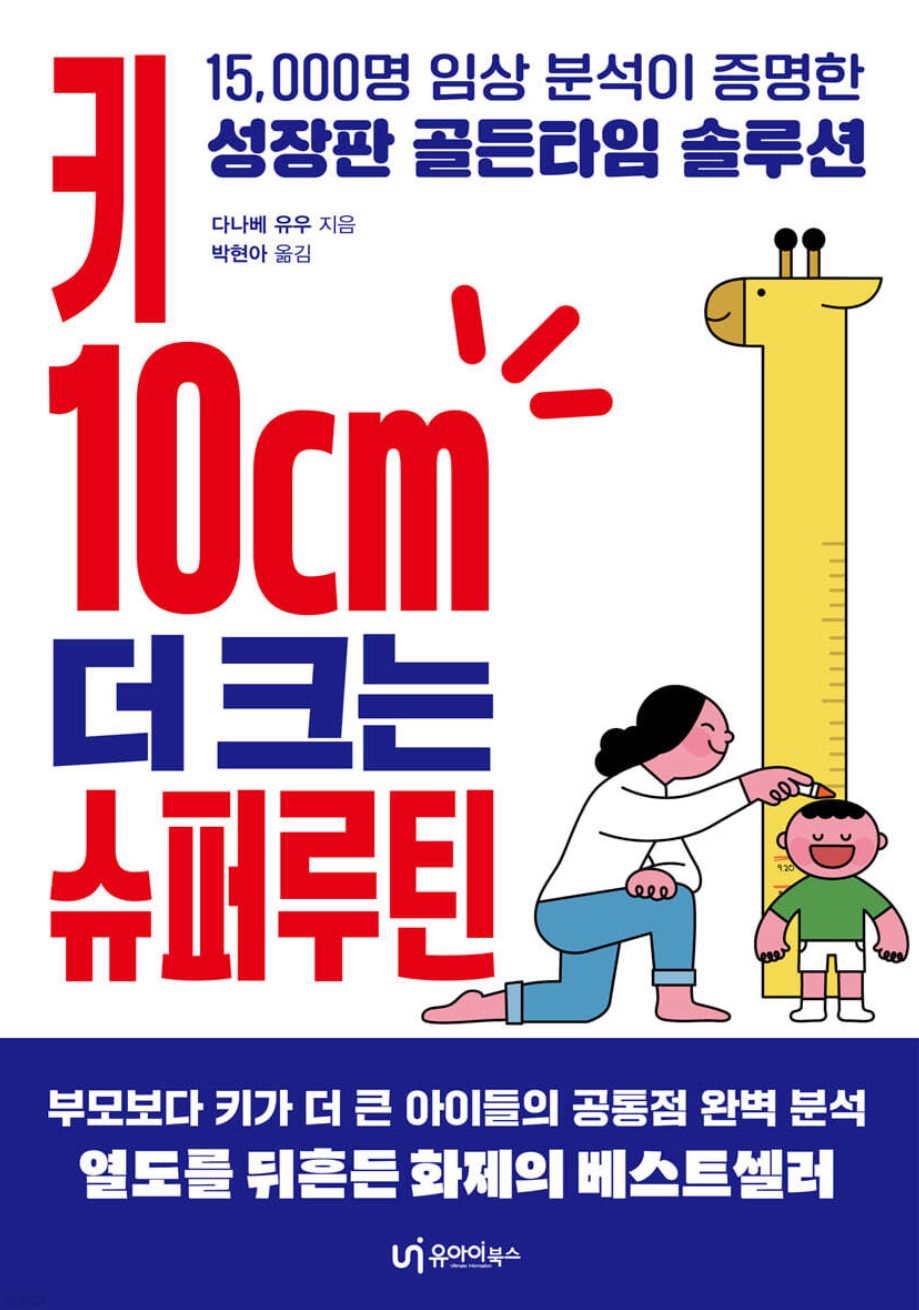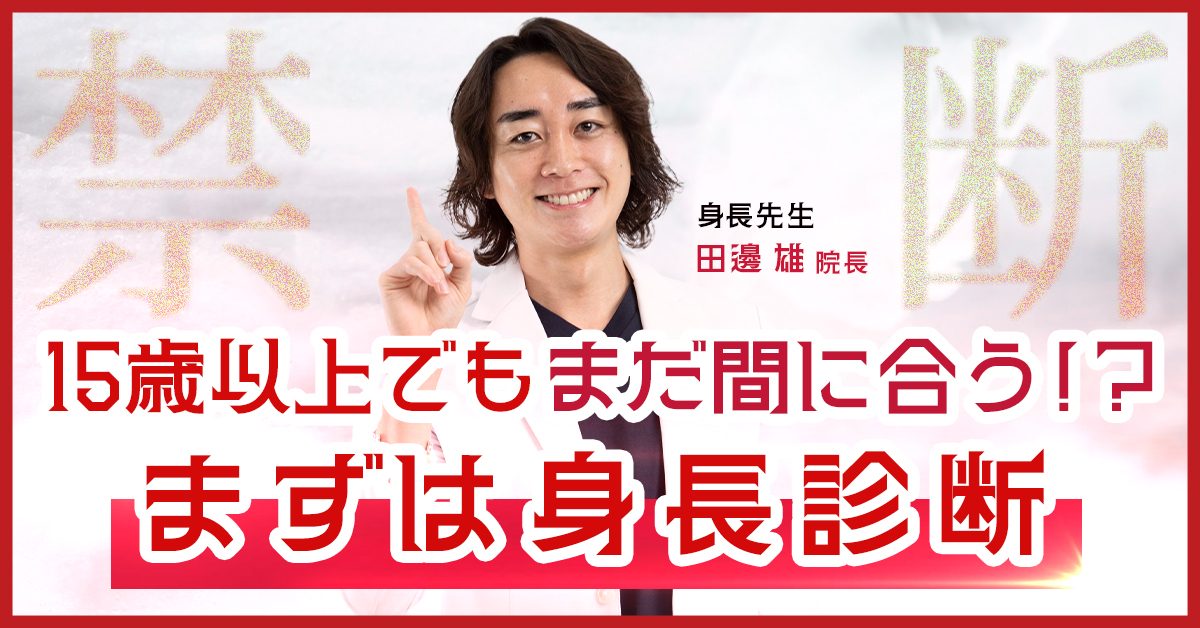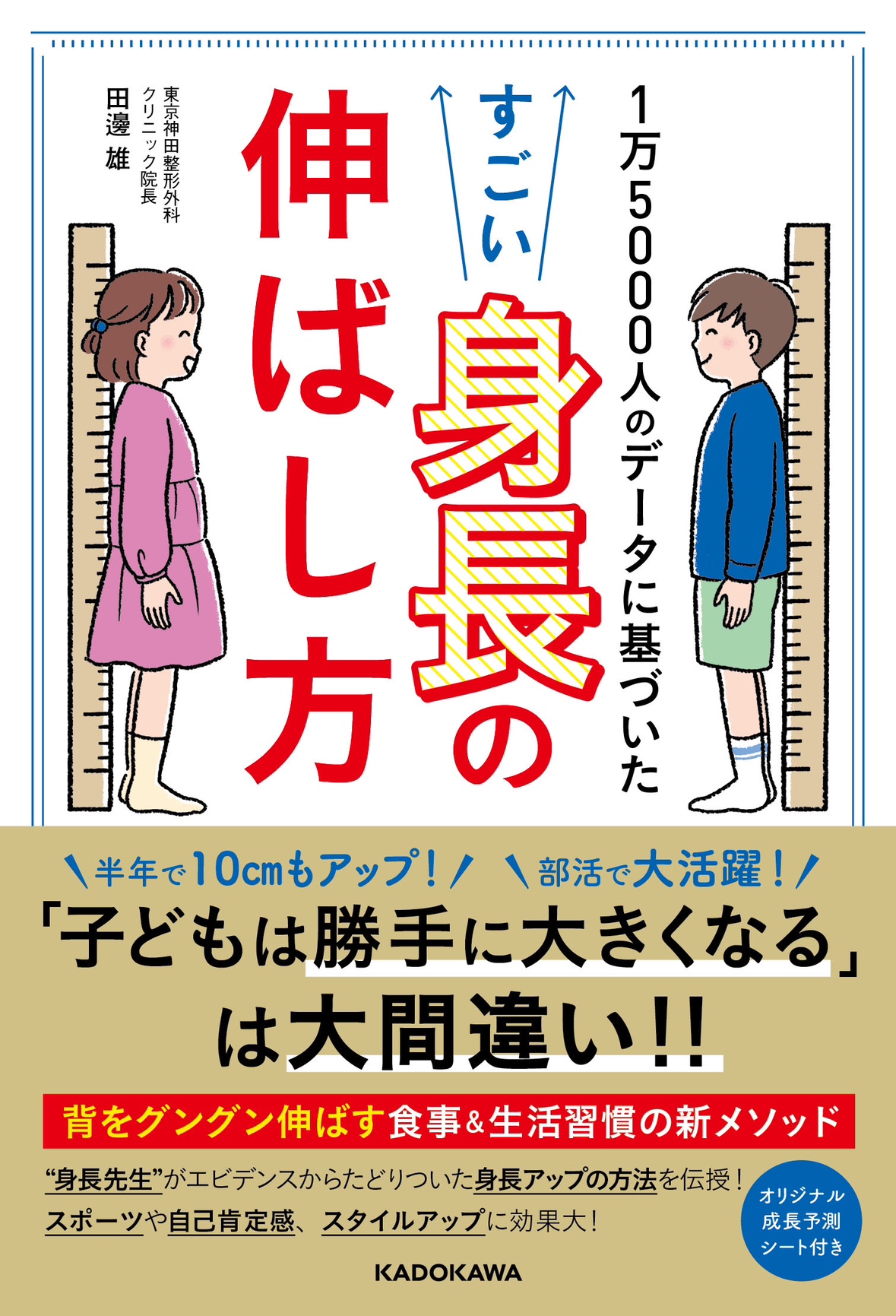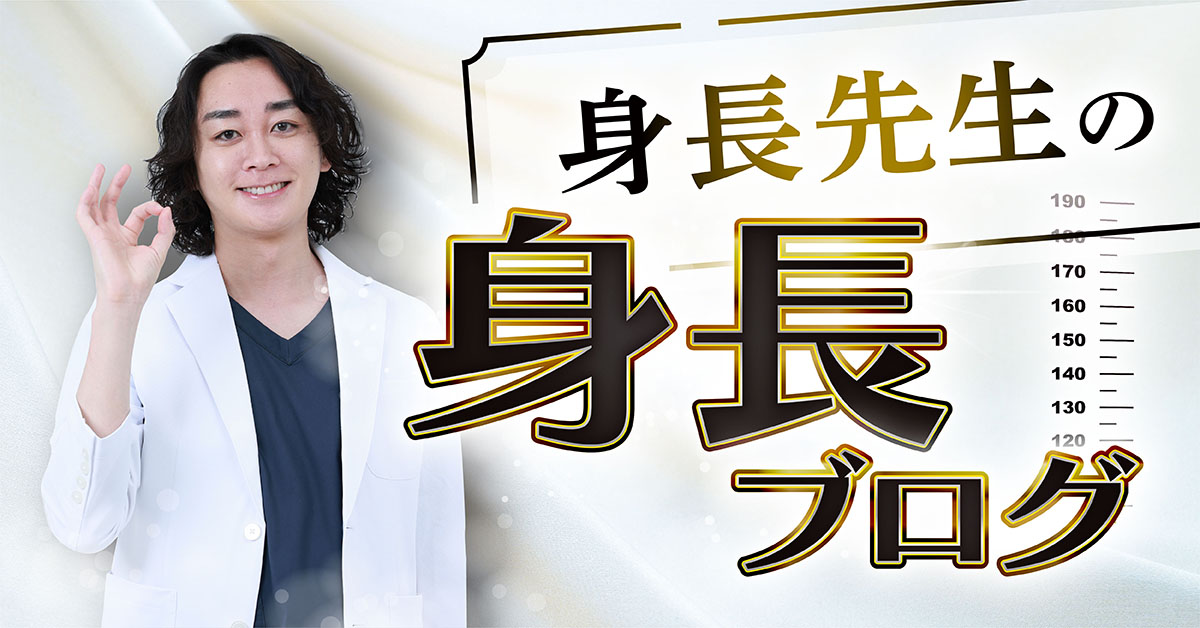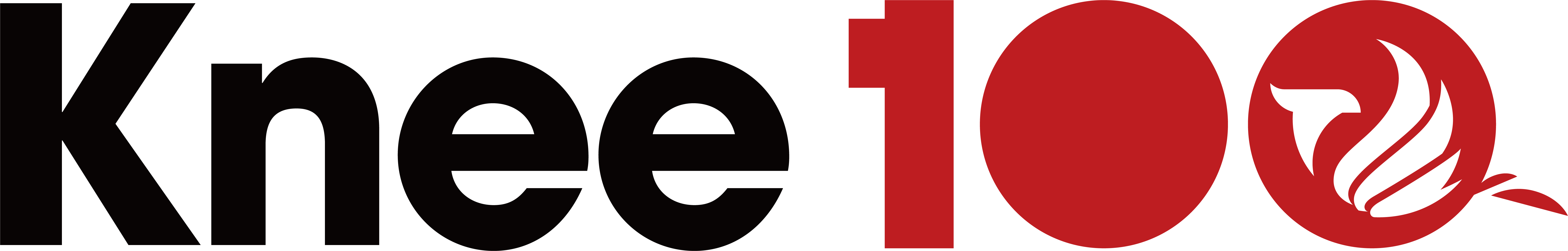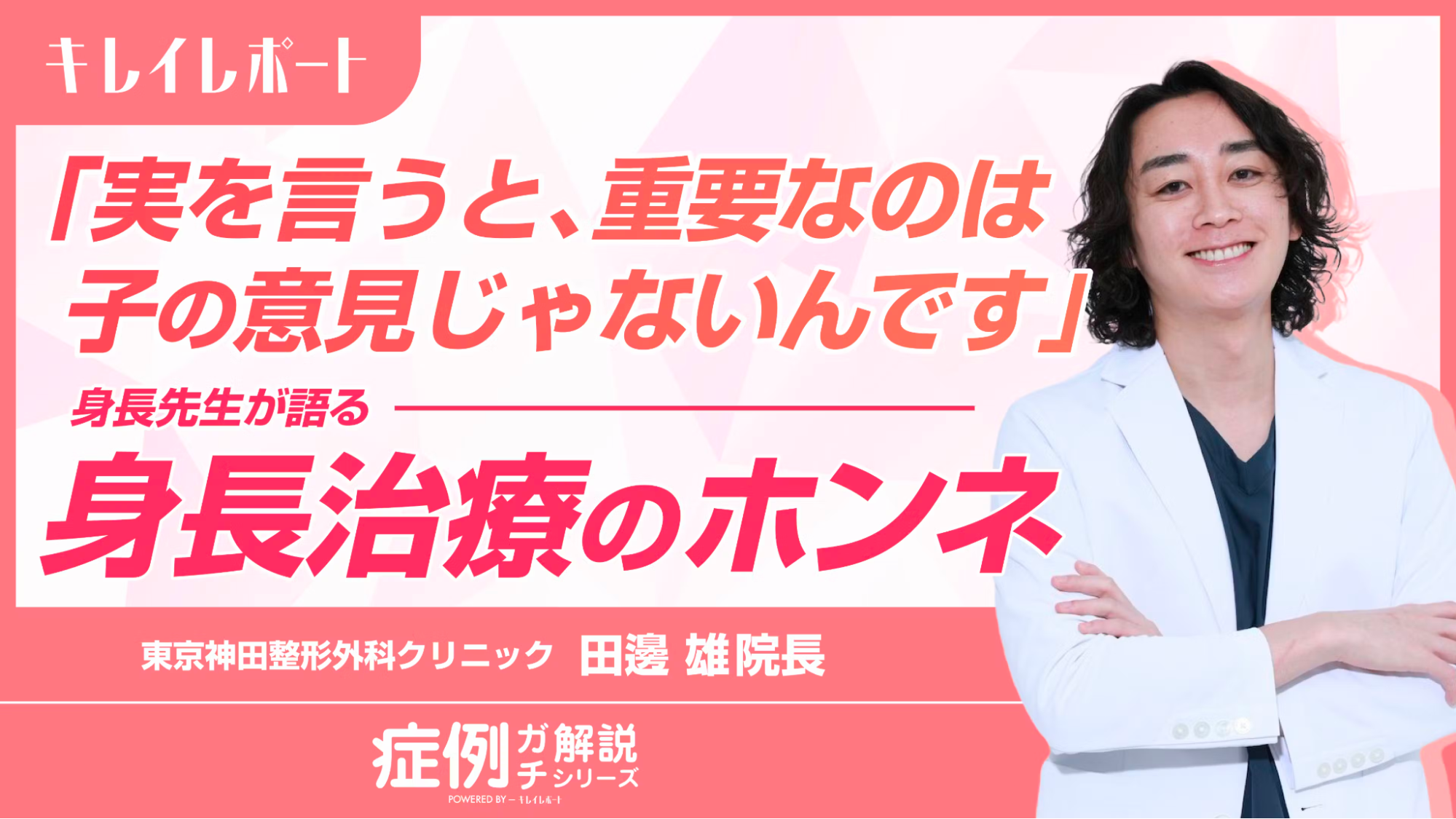成長ホルモンの分泌を増やす方法を解説!身長との関係性| 低身長治療・再生医療なら東京神田整形外科クリニック
「成長ホルモンを増やすと本当に身長が伸びるの?生活習慣で分泌を高める方法が知りたい」そう思う方もいるかもしれません。
実は、成長ホルモンは身長の伸びや体力・若々しさを左右する大切な要素で、生活習慣や工夫によって分泌を増やすことが可能です。
この記事では、成長ホルモンと身長の関係や、分泌を高めるための睡眠・食事・運動・サプリメントなどの具体的な方法を解説します。
成長ホルモンと身長の関係性とは?

成長ホルモンは、体の発達や代謝を支える重要な役割を持っています。特に成長期には、骨の伸びや筋肉の発達に大きく関わると言われています。
ここでは、成長ホルモンが身長にどのように影響するのかを分かりやすく解説します。
成長ホルモンとは
成長ホルモンとは、脳の下垂体と呼ばれる部分から分泌されるホルモンで、体の成長や発達を支える上で欠かせないものです。特に子どもの時期には、骨や筋肉を伸ばし、健康的に発達するための重要な役割を果たすと言われています。
このホルモンは一日中同じ量が出ているわけではなく、分泌にはリズムがあります。いわゆる体内時計(サーカディアンリズム)の影響を受け、特に眠りについてから約90分後の深い睡眠のタイミングで分泌のピークを迎えるとされています。また、日中であっても運動を行った後などに分泌が高まりやすいと考えられています。
つまり、成長ホルモンは睡眠や運動と深く関わり、骨端線に作用することで身長を伸ばす仕組みを持っているのです。
参照:The Journal of Clinical Investigation
身長を伸ばすには成長ホルモンの分泌が欠かせない
身長が伸びる仕組みには、骨の成長が大きく関わっています。特に骨の端にある「骨端線」と呼ばれる部分が活発に働く時期に、成長ホルモンが十分に分泌されることで骨が縦に伸び、身長の伸びにつながると言われています。
もし成長ホルモンの分泌が少ないと、しっかり睡眠を取ったり運動をしたりしても、思うように身長が伸びにくいことがあります。逆に、生活習慣を整えて分泌を高めていくことで、成長期の体はより効率的に発達すると考えられています。
特に骨端線が開いている時期は限られており、この期間に十分な成長ホルモンを分泌させることが将来の身長にとって大切なポイントになるのです。
成長ホルモンの分泌を増やす方法

成長ホルモンは自然な生活習慣の中で分泌を高めることができると言われています。特別なことをしなくても、睡眠の質を見直したり、栄養バランスの整った食事を心がけたり、日常的に体を動かすことが大切です。
ここからは、実生活に取り入れやすい具体的な方法を紹介していきます。
質の良い睡眠をとる
成長ホルモンは、眠っている間に特に多く分泌されると言われています。その中でもノンレム睡眠と呼ばれる深い眠りの時間帯に分泌がピークを迎えるため、睡眠の質がとても重要になります。
具体的には「寝る時間」「寝始め3時間の深さ」「毎日のリズム」が大きなカギになります。夜更かしを繰り返すと体内時計が乱れ、分泌が十分に行われにくくなるため、できるだけ同じ時間に寝て同じ時間に起きる習慣を意識することが大切です。
また、必要な睡眠時間は年齢によって異なると考えられています。小学生は9〜11時間、中高生は8〜10時間、成人は7〜9時間程度が目安とされています。自分の年齢に合った睡眠を確保し、寝始めの3時間で深く眠れるように環境を整えることで、成長ホルモンの分泌をより高めることができるのです。
バランスのとれた食事をとる
成長ホルモンの分泌を助けるためには、食事の内容が大きな役割を果たします。特に重要なのはタンパク質で、体の成長に必要な必須アミノ酸が成長ホルモンの材料になると言われています。肉や魚、卵、乳製品などをバランスよく取り入れることが基本です。
さらに、ビタミンやミネラルも分泌を支える要素と考えられています。中でも亜鉛やマグネシウムはホルモンの働きに関わり、ビタミンDは骨の成長や吸収に影響を与えるとされています。これらを意識的に摂取することで、成長ホルモンの働きをより効果的に引き出せる可能性があります。
一方で、糖質を過剰にとったり、間食を頻繁に食べたりすると、インスリンが過剰に分泌されることがあります。その結果、成長ホルモンの分泌が抑えられると考えられているため、食事の質と量のバランスを見直すことも大切です。
適度な運動をする
成長ホルモンは、運動をするときにも分泌が高まると言われています。特にジョギングや縄跳びなどの有酸素運動、そして体全体を使う運動は分泌を促す効果が期待できると考えられています。
その中でも「ややきつい」と感じる程度の負荷をかけることがポイントになります。軽すぎる運動では分泌の刺激が弱くなり、逆に過度な運動では体に負担がかかりすぎるため、適度な強度を保つことが大切です。理想的には、週に3回以上を目安に継続して行うとよいとされています。
また、無理に難しいトレーニングを取り入れる必要はありません。自分が楽しんで続けられる運動をベースに、全身をしっかりと動かすことが、長期的に成長ホルモンの分泌を支える習慣につながります。
参照:Journal of Applied Physiology
ストレスをためない
成長ホルモンの分泌には、心の状態も深く関わっていると言われています。強いストレスを受け続けると、体内で「コルチゾール」と呼ばれるホルモンが増加しやすくなります。このコルチゾールは体を守るために必要な働きを持っていますが、過剰に分泌されると成長ホルモンの働きを妨げると考えられています。
特に成長期の子どもにとっては、学校や家庭でのストレスが大きな影響を与えることがあります。例えば学業のプレッシャーや人間関係の不安、家庭内での緊張した雰囲気などは、知らず知らずのうちに体のホルモンバランスに影響する可能性があります。
そのため、日常生活の中でリラックスできる時間を意識的に作ることが大切です。趣味に没頭したり、家族との会話を楽しんだり、好きな音楽を聴いたりすることが、ストレスを和らげる助けになります。このような工夫が心の安定につながり、結果として成長ホルモンの分泌を支えることになるのです。
夜のスマホやゲームは控える
夜にスマホやゲームを長時間使うと、眠りの質が下がると言われています。画面から出るブルーライトは脳を刺激し、眠気を感じにくくするため、成長ホルモンが分泌されやすい就寝直後の深い眠りを妨げる可能性があります。その結果、分泌のタイミングを逃してしまうことにつながるのです。
特に意識したいのは「寝る1時間前はデジタルデトックスをする」という習慣です。スマホやゲームを控えることで、自然と眠りに入りやすくなり、成長ホルモンの分泌リズムを整えやすくなります。
また、子どもの場合は親の声かけや管理も大切になります。「そろそろ寝る時間だから画面を消そうね」といった一言や、家庭全体で夜はリラックスする時間を作る工夫が役立ちます。こうした取り組みを家族で続けることが、結果的に健康的な生活リズムを支え、成長ホルモンの分泌にも良い影響を与えるのです。
参照:京田辺市「睡眠とスマートフォンの関係」
小児身長治療を検討する
生活習慣を整えても、周囲のお子さんと比べて明らかに身長が低く、このままでは将来の成長が心配だと感じる方もいるかもしれません。そのような場合には、小児身長治療を検討するという選択肢もあります。
東京神田整形外科クリニックでは、骨端線の状態や成長ホルモンの分泌状況を確認しながら、一人ひとりに合わせたアプローチが行われていると紹介されています。具体的には、ホルモンの働きを補助する方法や、成長のタイミングを見極めたうえでの施術方針があり、いずれも安全性や効果を踏まえて検討されているようです。
もし「子どもの身長をもう少し伸ばしてあげたい」と思っている場合は、早めに専門機関に相談してみることが大切です。まずは問い合わせをして情報を集めることから始めると、今後の方針を考える上で安心につながります。
小児身長治療に関しては、こちらのYouTubeで詳しく解説しましたので合わせてご確認ください。
成長ホルモンの分泌を増やすサプリメントは?

成長ホルモンの分泌を増やすために、サプリメントを取り入れたいと考える方もいるかもしれません。ただし、成長ホルモンそのものを“直接的に増やす”サプリメントは存在しないとされています。そのため、あくまでも不足しがちな栄養素を補助的に取り入れるという位置づけで考えることが大切です。
サプリメントの中では、アルギニンや亜鉛、マグネシウムといった栄養素が成長ホルモンの働きを間接的に支えるものとして知られています。これらは食事からも摂取可能ですが、忙しい生活や偏った食事になりがちな場合には、サプリメントで補うことが役立つ場合があります。
ただし注意したいのは、市販のサプリメントを自己判断で過剰に摂取することです。過剰摂取は体に負担をかける可能性があるため、必ず「食事の補助」という目的を忘れないことが重要です。必要に応じて専門家の意見を取り入れながら、正しく使うようにしましょう。
サプリメントに関しては、こちらのYouTubeで詳しく解説しましたので合わせてご確認ください。
成長ホルモンが分泌されないとどうなる?

成長ホルモンは、身長の伸びだけでなく、筋肉や骨の健康、そして体の回復力にも深く関わっていると言われています。そのため、分泌が不足すると体にさまざまな変化が現れる可能性があります。
ここでは、成長ホルモンが十分に分泌されない場合にどのような影響があるのかを具体的に見ていきましょう。
身長の伸びが止まる
骨が成長するためには、骨端線と呼ばれる部分が活発に働いている必要があります。骨端線が開いていても、成長ホルモンが不足していると骨の伸びが不十分になり、結果として身長の伸びが止まってしまう可能性があると言われています。
このような状態が続くと、平均よりも大きく低い身長で成長が止まってしまうこともあります。中には「成長ホルモン分泌不全性低身長症(GHD)」と呼ばれる病気が関係している場合もあり、注意が必要とされています。
つまり、骨端線がまだ残っている成長期の間に、十分な成長ホルモンの分泌を確保することが、将来の身長を左右する大切な要素になるのです。
筋肉量の減少し脂肪が蓄積される
成長ホルモンは、骨の成長だけでなく筋肉の発達にも深く関わっていると言われています。そのため、分泌が不足すると筋肉量が減少しやすくなり、同時に脂肪がつきやすい体質へと傾いてしまうことがあります。
特に成長期の子どもにとっては、筋肉量が減ることで体力の低下につながることが懸念されます。また、筋肉が少なくなると基礎代謝が落ちやすくなり、結果的に体内に脂肪が蓄積しやすくなると考えられています。
このように、成長ホルモンの不足は身長の伸びだけでなく、体力や代謝の面にも影響を与えるため、日常生活の中で分泌を促す工夫をすることが重要になります。
骨密度の低下
成長ホルモンは骨の長さを伸ばすだけでなく、骨を強くする「骨形成」にも関わっているとされています。そのため、分泌が不足すると骨の密度が十分に高まらず、将来的に骨粗しょう症のリスクが高まる可能性があります。
特に子どもの時期は、骨の基礎を作る大切な期間です。この時期に成長ホルモンが十分に働かないと、骨が丈夫に育たず、成人後の健康にも影響が及ぶことが考えられます。
つまり、成長期にしっかりと成長ホルモンを分泌させ、骨密度を高めておくことが、将来の骨の強さを守るために重要なポイントになるのです。
疲れやすくなる
成長ホルモンは、体の成長や代謝だけでなく、免疫機能にも関わっていると言われています。そのため、分泌が不足すると免疫力が下がり、風邪などの感染症にかかりやすくなる可能性があります。
また、成長ホルモンはエネルギー代謝を支える働きも持っています。分泌が少ないとエネルギーの供給が不十分になり、日常生活の中で疲れやすさを感じやすくなるのです。
このように、成長ホルモンが不足すると体力面だけでなく健康全般に影響を及ぼすため、生活習慣の見直しによって分泌を促すことが大切だと考えられています。
成長ホルモンを増やすことに関するよくある質問

成長ホルモンについては「成長ホルモンを増やすには?」「成長ホルモンが出ない理由は?」といった疑問を持つ方が多いようです。
ここでは、よく寄せられる質問を取り上げながら、成長ホルモンに関する基本的な考え方を整理していきます。
成長ホルモンを増やすツボはありますか?
ツボ刺激によって成長ホルモンが増えるのではないかと考える方もいます。一般的に知られているツボには、頭頂部にある「百会」や、手足にある「成長点」などがあります。これらを刺激すると血流が良くなり、リラックス効果が期待できると言われています。
ただし、ツボを押すことで直接的に成長ホルモンが増えるという科学的な根拠は、現時点では十分ではありません。そのため、成長ホルモンの分泌を目的にツボだけに頼るのではなく、あくまでリラクゼーションやストレス解消の一環として取り入れるのが良いでしょう。
無理なく気持ちよく続けられる範囲で取り入れることで、心身のリフレッシュにつながり、間接的に成長ホルモンを支える効果が期待できるかもしれません。
よく寝る子は身長が伸びやすいですか?
一般的に「よく眠る子は背が高くなる」と言われることがあります。実際、深い眠りの時間帯に成長ホルモンが多く分泌されるため、よく眠る子どもはホルモンの分泌が安定しており、その結果として身長が伸びやすい傾向があると考えられています。
ただし、大切なのは睡眠の“長さ”だけではありません。長時間寝ていても浅い眠りばかりでは十分な分泌が得られにくいのです。寝始めの3時間に深い眠りをしっかりと確保できるように、生活リズムを整え、質の良い睡眠をとることが成長にとって重要だと言えるでしょう。
成長ホルモンが出ない理由はなんですか?
成長ホルモンが十分に分泌されない背景には、いくつかの要因があると考えられています。まず多いのは日常生活に関わるもので、睡眠不足や栄養の偏り、強いストレスなどが代表的な原因です。これらの生活習慣が乱れると、成長ホルモンの分泌リズムが崩れやすくなります。
一方で、下垂体の異常など病気が関わっている場合もあります。これは生活習慣だけでは改善が難しいケースであり、専門的な検査や対応が必要になることもあります。
つまり、成長ホルモンが出ない理由には生活習慣と病気の両面があるため、まずは睡眠や食事、ストレス管理を整えることが第一歩です。そのうえで改善が見られない場合には、専門機関に相談して検査を受けることが望ましいとされています。
参照:繊維機械学会誌「快適ライフのための睡眠」
まとめ
成長ホルモンは、身長の伸びや筋肉・骨の発達、さらには体力や免疫の維持にも関わる大切なホルモンです。特に成長期には、骨端線が開いている期間にしっかりと分泌させることが、将来の身長や健康状態に大きく影響すると言われています。
分泌を高めるためには、質の良い睡眠、栄養バランスの整った食事、適度な運動、ストレスの軽減、そして夜のスマホやゲームを控えるといった日常生活の工夫が大切です。また、どうしても周囲と比べて身長が気になる場合には、小児身長治療を検討することも一つの選択肢となります。
・両親の身長が低く、子どもの発育に不安がある
・身長を伸ばしたいが適切なサポート方法を知りたい
・他の医院では、「特に治療の必要はありません」と断られた
東京神田整形外科クリニックの小児身長治療ならば、将来160センチまで成長する予定のお子さんが、しっかり治療を受ければ最大で+15センチぐらいの身長を目指せます。
5〜15歳のお子さんを対象に治療を提供しておりますので、今後も身長について悩まれるときは、ぜひご検討ください。
また、身長先生こと、医院長の田邊がお子さんの将来の身長を予測する「身長先生の身長診断」も完全予約制でご用意しています。お子さんの身長を伸ばしていきたいと考えるときは、ご確認ください。
監修者

院長 (全日出勤)
田邊 雄 (たなべ ゆう)
経歴
2011年 金沢医科大学卒業
2018年 日本整形外科学会認定整形外科専門医取得
2018年 順天堂大学博士号取得
2020年 東京神田整形外科クリニック開業

再生医療リードドクター (毎週月曜日、第1・3・5土曜日勤務)
横田 直正 (よこた なおまさ)
経歴
平成11年3月 国立浜松医科大学医学部卒業
平成11年4月~平成18年12月 東京大学医学部整形外科在籍
平成11年5月~平成11年12月 東京大学医学部付属病院整形外科
平成12年1月~平成12年6月 東京逓信病院麻酔科
平成12年7月~平成13年6月 三楽病院整形外科
平成13年7月~平成14年12月 都立広尾病院整形外科
平成15年1月~平成16年6月 東芝林間病院整形外科
平成16年7月~平成17年9月 多摩北部医療センター整形外科
平成17年10月~平成18年9月 都立墨東病院リウマチ膠原病科
平成18年10月~平成19年12月 東京逓信病院整形外科
平成19年7月~平成27年2月 太秦病院整形外科リウマチ科
平成27年3月~平成29年3月 富士見病院整形外科
平成28年6月~平成29年3月 東京ひざ関節症クリニック銀座(院長)
平成29年4月~令和3年4月 東京ひざ関節症クリニック新宿(院長)
令和3年5月~ 総合クリニックドクターランド、新山手病院など

医師 (水曜日勤務)
斎藤 吉由 (さいとう よしゆき)
経歴
1989年 久留米大学 医学部卒業
1990-2000年 久留米大学整形外科医局
2000年-
クリニックヨコヤマ 副院長
泉ガーデンクリニック 整形外科医長
東京ミッドタウンクリニック 整形外科部長
医療法人財団 百葉の会 銀座医院 副院長 等を歴任