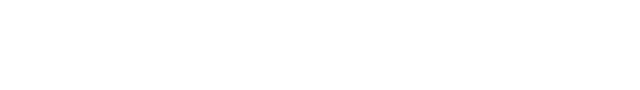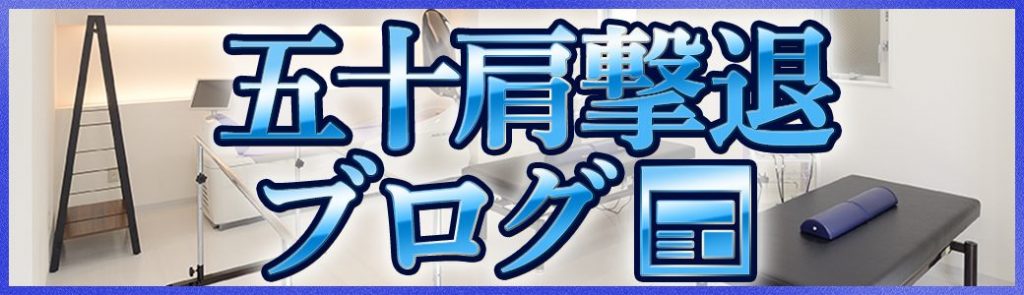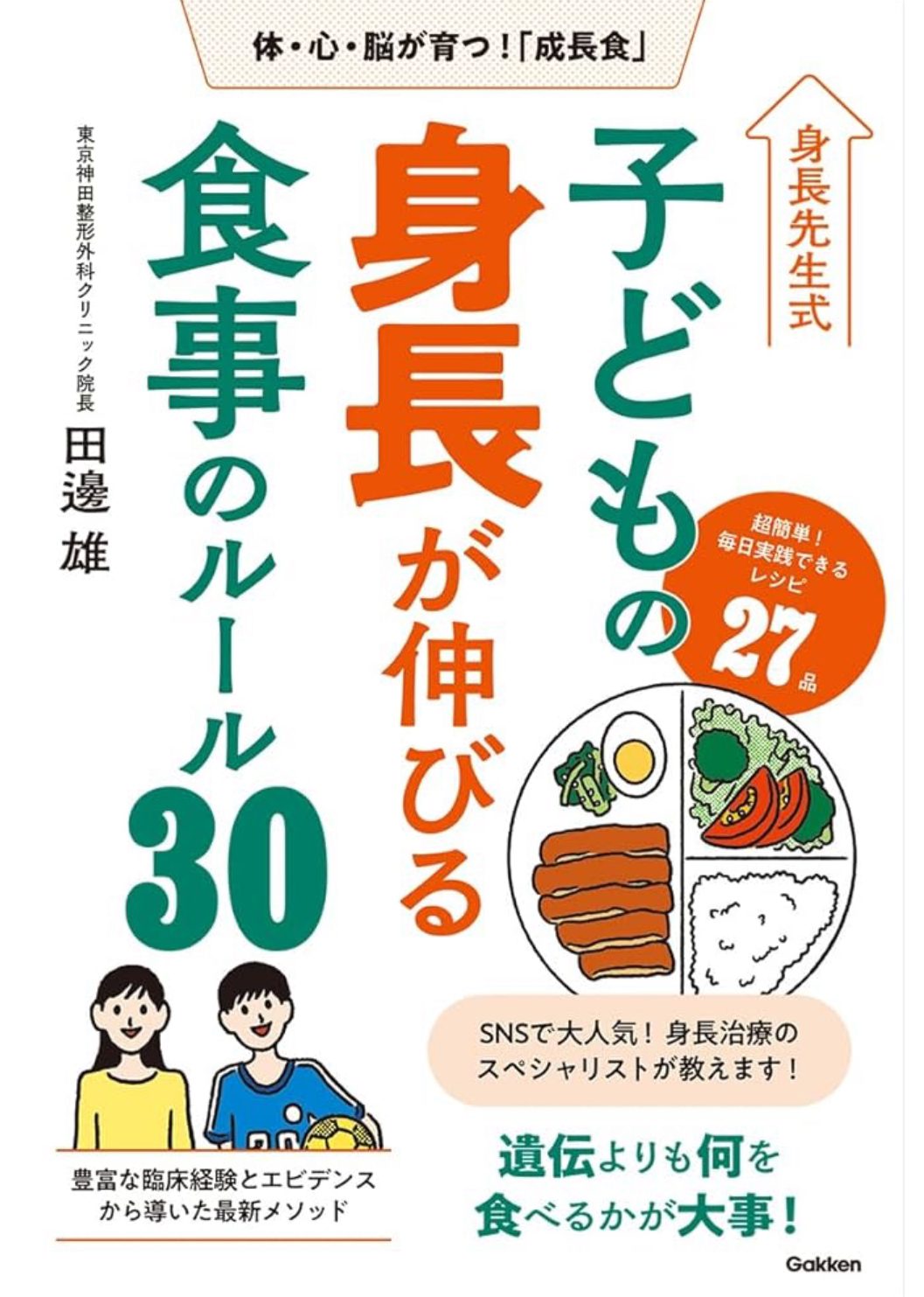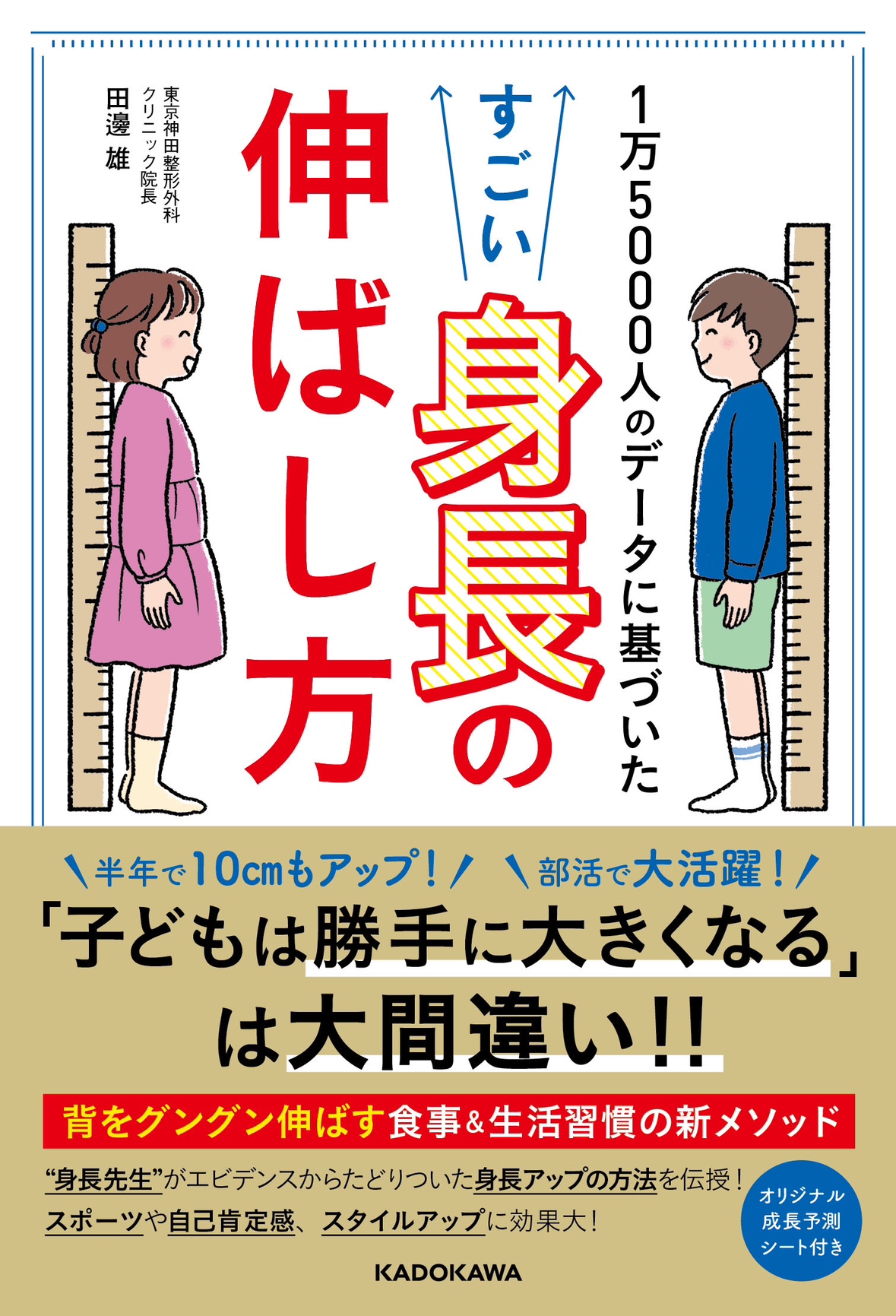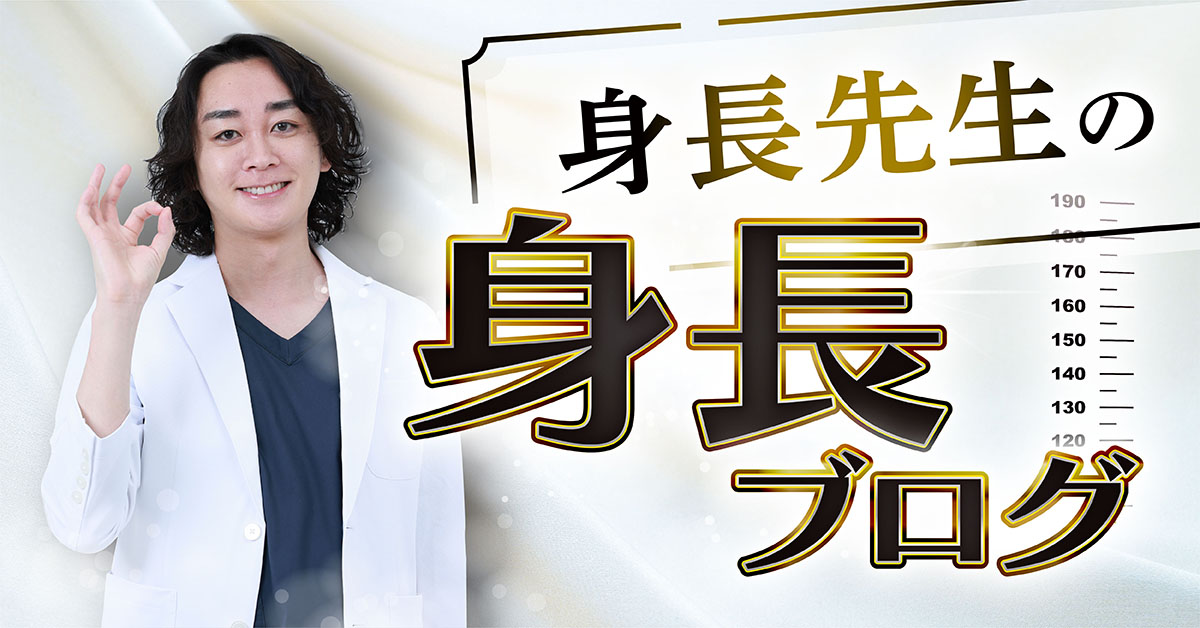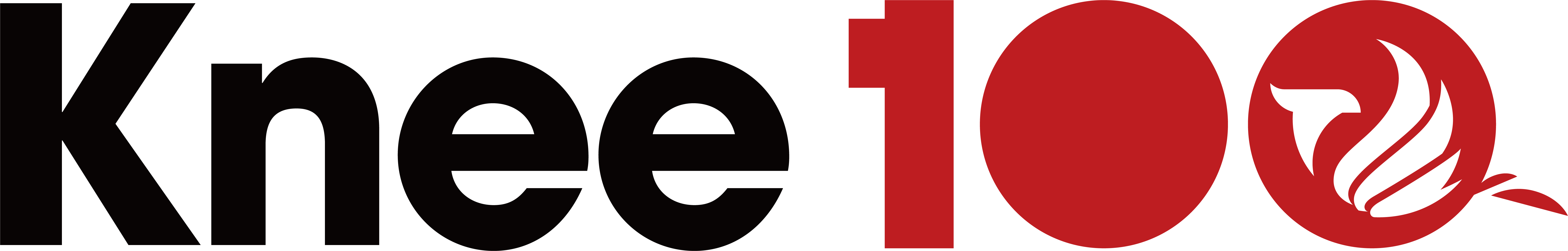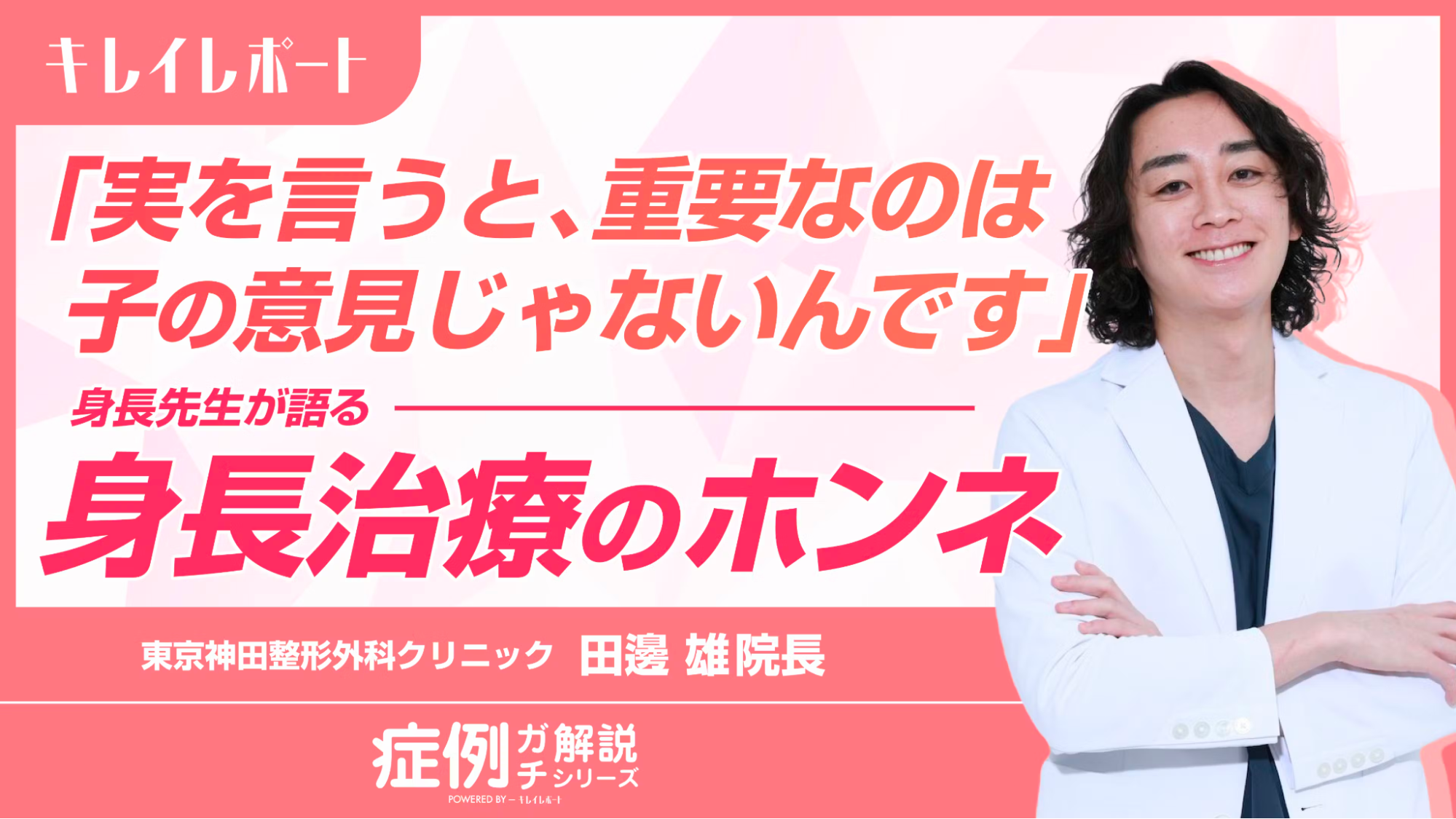巻き肩や猫背の原因を徹底解説!筋肉と寝方が与える影響とその対策3選

「巻き肩や猫背の原因って何だろう?」「最近、肩や背中が痛くて、姿勢が悪い気がする…改善する方法はないのかな?」そう思う方もいるかもしれません。
実は、巻き肩や猫背の原因は筋肉と寝方に大きく影響されています。これらを見直すことで、姿勢の改善が可能です。
この記事では、巻き肩や猫背の原因となる筋肉の使い方や寝方について詳しく解説し、それに対する効果的な対策を3つご紹介します。
目次
巻き肩や猫背の原因と症状

巻き肩や猫背の正しい理解は、効果的な対策を講じるための第一歩です。
まずはそれぞれの特徴と、どのように体に影響を与えるのかをしっかり把握していきましょう。
巻き肩と猫背の違いとは?
巻き肩と猫背は、姿勢の問題でありながら、異なる特徴を持っています。
巻き肩
巻き肩は肩が前方に突き出し、肩甲骨が前方に移動した状態です。
これにより、胸郭が前に突き出しているように見えます。
主な原因は長時間のデスクワークやスマートフォンの使用など前かがみの姿勢です。
巻き肩では胸部の筋肉が縮まり、背中の筋肉が伸ばされた状態が続くため、弱くなる可能性もあります。
外見的には肩が前に出て胸が張った印象を与えます。
猫背
猫背は背骨の上部が後方に丸まり、頭部が前に突き出した状態です。
背中の上部が丸まり、胸が内側に収縮して見えます。
原因としては背中の筋力低下や長時間の悪い姿勢が挙げられ、猫背になると背中の筋肉が伸び胸部の筋肉が縮まります。
外見的には背中が丸まって胸が凹んだ印象を与えるでしょう。
巻き肩と猫背は、どちらも姿勢の問題であり、肩こりや首の痛みを引き起こすことがありますが、それぞれの特徴と影響は異なります。
巻き肩や猫背が引き起こす体への影響
筋骨格系への影響
巻き肩や猫背は、肩こりや首の痛みを引き起こしやすいです。
また、胸郭や横隔膜の機能不全が生じて姿勢制御に悪影響を与え、腰痛を悪化させる可能性もあります。
肩周りの筋肉が緊張し、身体の不調を引き起こすこともあるかもしれません。
長期的には、これらの問題が慢性化し、生活の質を低下させる可能性があります。
呼吸への影響
姿勢が悪化すると、呼吸が浅くなり、息苦しさを感じることがあります。
胸郭が圧迫されることで、横隔膜の機能が低下する可能性もあります。
これにより、酸素の取り込みが不十分になり、疲れやすさを感じることがあるかもしれません。
神経系への影響
巻き肩や猫背は、腕周囲の筋肉の緊張により痺れを感じることがあり、神経圧迫が起こることがあります。
この神経圧迫が原因で、体に痛みが生じてしまう可能性もあるでしょう。
精神的影響
姿勢の問題は、身体的ストレスだけでなく、精神的なストレスにもつながることがあります。
自律神経のバランスが乱れると、心身の回復力が低下し、様々な不調のリスクが高まります。
巻き肩や猫背は、見た目の問題だけでなく、胸郭や横隔膜などの姿勢制御に関わる部位へ悪影響を与える可能性があります。
その悪影響が、腰痛を引き起こすこともあるため、早期に対策を講じることが重要です。
筋肉の使い方が引き起こす巻き肩の原因
巻き肩を防ぐためには、筋肉の使い方を見直し、バランスのいいストレッチやエクササイズを行うことが重要です。
特に、肩や背中の筋肉を均等に鍛え、姿勢を改善することが大切なポイント。
どの筋肉が巻き肩に影響を与えるのか
巻き肩に影響を与える筋肉として、以下の筋群が挙げられます。
- 胸部の筋肉
- 背中の筋肉
- 肩甲骨周辺の筋肉
胸部の筋肉
胸部の筋肉(大胸筋や小胸筋など)が過度に使われると、肩が前方に引っ張られ、巻き肩が進行します。
特に、デスクワークやスマートフォンの操作など、前かがみの姿勢が続くと、これらの筋肉が緊張しやすくなります。
背中の筋肉
背中に位置する広背筋は肩関節の動きや姿勢維持に重要な筋肉ですが、過度な緊張状態にあると肩甲骨が前方に引っ張られ、巻き肩の原因になることがあります。
特に、他の肩周りの筋肉とのバランスが崩れると、姿勢不良や痛みを引き起こす可能性が高まります。
肩甲骨周辺の筋肉
肩甲骨周辺の筋肉(前鋸筋や肩甲下筋)も、巻き肩に大きな影響を与えます。
これらの筋肉が緊張していると、肩甲骨が前に移動しやすくなり、巻き肩が進行します。
巻き肩を改善するためには、これらの筋肉を均等に動かし、姿勢を正すことが必要です。
巻き肩の主な原因として、筋肉のバランスが崩れることが挙げられます。
特に、前方と後方の筋肉のバランスが崩れることで、巻き肩が進行します。
筋肉のバランスが崩れると、肩甲骨の安定性を低下させ、姿勢に影響を与えるでしょう。
筋肉のバランスが崩れる理由

前後の問題
巻き肩は、前方に傾く筋肉と後方に引っ張る筋肉のバランスが崩れることで発生します。
具体的には、以下のような問題があります。
前方の筋肉の過度な緊張
胸部の筋肉(大胸筋や小胸筋)が過度に緊張し、肩を前方に引っ張ります。
後方の筋肉の弱体化
背中の筋肉(僧帽筋や広背筋など)が弱くなると、肩甲骨を後方に引き戻す力が不足します。
このため、肩甲骨が安定せず、前方に巻き込まれやすくなります。
肩甲骨の安定性低下
筋肉のバランスが崩れることにより、肩甲骨の位置が安定しなくなります。
肩甲骨周囲の筋肉(前鋸筋や肩甲下筋など)のバランスが崩れると、肩甲骨の適切な位置保持が困難になります。
その結果、肩甲骨が前方に巻き込まれやすくなり、巻き肩が進行してしまうでしょう。
日常生活の影響
特定の姿勢や動作の繰り返しが、筋肉のバランスの崩れを助長します。
例えば、デスクワークやスマートフォンの使用など、前かがみの姿勢が続くと、前方の筋肉が短縮し、後方の筋肉が伸びきった状態になります。
この状態が継続すると、筋肉のバランスの崩れがさらに悪化し、巻き肩が進行するでしょう。
筋肉のバランスの崩れを改善するためには、ストレッチや適切な筋力トレーニングを行い、前方と後方の筋肉のバランスを整えることが重要です。
また、日常生活での姿勢にも注意を払い、肩甲骨を後方に引き付ける意識を持つことが巻き肩の予防と改善につながります。
寝方が巻き肩や猫背に与える影響

私たちが毎晩の睡眠中に取る姿勢は、身体に大きな影響を及ぼします。
ここでは、寝方がどのようにこれらの姿勢の問題に影響を与えるのか、また正しい寝方と間違った寝方の違い、そして長期的な影響について詳しく見ていきましょう。
正しい寝方と間違った寝方の違い
寝方によって、巻き肩や猫背の進行に影響を与えることがあります。
正しい寝方と間違った寝方の違いを理解することで、姿勢の改善に役立てることができます。
正しい寝方
正しい寝方は、体に負担をかけず、自然な姿勢を保つものです。
仰向けに寝ることが推奨されることが多いですが、横向きで寝る場合も注意が必要です。具体的には以下の点に注意しましょう。
仰向けで寝る場合
頭と首が中立の位置に保たれるようにし、背中全体を均等に支えるマットレスを使用します。
膝の下にクッションを置くことで、腰への負担を軽減できます。
横向きで寝る場合
脚を軽く曲げ、膝と肩の位置が自然に保たれるようにします。
肩の下に十分なサポートを提供する枕を使用し、腰を直線に保つことが重要です。
間違った寝方
間違った寝方は、姿勢に不自然な圧力をかけ、巻き肩や猫背を悪化させる可能性があります。
以下のような寝方が問題です。
うつ伏せで寝る場合
首を無理にひねることになり、肩や背中に余分な負担がかかります。
これが巻き肩や猫背を引き起こす原因となることがあります。
高すぎる枕を使用する場合
頭や首が不自然な角度で保持されることで、肩甲骨や背中の筋肉に負担がかかります。
寝方が巻き肩や猫背に与える長期的な影響
寝方が姿勢に与える影響は、短期間では感じられないかもしれませんが、長期的に見ると大きな変化をもたらします。
以下は、寝方が巻き肩や猫背に与える長期的な影響です。
- 巻き肩の悪化
- 猫背の進行
- 筋肉の緊張と痛み
巻き肩の悪化
不適切な寝方は、肩の位置を悪化させ、巻き肩を進行させる可能性があります。
これが長期間続くと、巻き肩がより顕著になることがあります。
猫背の進行
寝方が猫背に影響を与えることもあります。
適切なサポートがないと、背中の筋肉が不自然に伸びた状態が続き、猫背が悪化することがあります。
筋肉の緊張と痛み
不適切な寝方は、筋肉の緊張を引き起こし、肩や背中に痛みをもたらすことがあります。
これが慢性的な問題として続くと、姿勢に悪影響を及ぼし、巻き肩や猫背を引き起こす原因となります。
長期的に健康的な姿勢を保つためには、正しい寝方を心がけることが重要です。
寝具の選び方や寝る姿勢に注意を払い、毎晩の睡眠が姿勢に与える影響を最小限に抑えましょう。
巻き肩と猫背を改善する3つの対策
巻き肩や猫背を改善するためには、いくつかの対策を講じることが重要です。
ここでは、筋肉バランスを整えるストレッチ方法、正しい姿勢を保つためのエクササイズ、そして寝方の見直しと改善方法について詳しく解説します。
筋肉バランスを整えるストレッチ方法
胸部の筋肉(大胸筋や小胸筋)が短縮している場合、肩が前方に引っ張られやすくなります。
胸部のストレッチを行うことで、これらの筋肉をほぐし、肩の位置を改善する助けになります。
ドアフレームストレッチ
- ドアフレームの前に立ちます。
- 両腕を肘が90度になるように曲げ、ドアフレームの両側に置きます。
- 片足を前に踏み出し、上体をゆっくりと前に傾けます。
- 胸に伸びを感じる位置で15〜30秒間保持します。
このストレッチでは、大胸筋全体を効果的に伸ばすことができます。
正しい姿勢を保つためのエクササイズ
道具を使わずに簡単に実施できる、巻き肩を緩和する背中のエクササイズとして、「肩甲骨寄せ」をおすすめします。
コブラエクササイズ
- 床でうつ伏せになり、両腕を体側でハの字に開きます。
- 手のひらを床に向けるて、両足は腰幅で開いて爪先を立てます。
- みぞおちの少し手前まで胸を反らして上体を起こします。
- その状態でゆったり呼吸しながら30秒キープする。
- 同じ動作を3回程度繰り返しましょう。
このエクササイズは、背中の筋肉、特に僧帽筋下部を鍛えることで、肩甲骨の安定性を高め、巻き肩の改善に効果的です。
寝方の見直しと改善方法
寝方が姿勢に与える影響を最小限にするために、以下のポイントを心がけましょう。
- 寝具の選び方
- マットレス
- 枕
- 良い寝姿勢を心がける
- 寝具の選び方
適切な寝具を選ぶことで、睡眠中の姿勢をサポートし、巻き肩や猫背の進行を防ぐことができます。
- マットレス: 体を均等に支える中程度の硬さのマットレスが推奨されます。
柔らかすぎると体が沈み込み、硬すぎると体に圧力がかかります。
- 枕: 頭と首が自然な位置に保たれる高さの枕を選びましょう。
高さが合わない枕は首に負担をかけることがあります。
- 良い寝姿勢を心がける
寝る姿勢も姿勢の改善に役立ちます。
適切な寝姿勢を保つことで、巻き肩や猫背の予防になります。
- 仰向けで寝る: 仰向けで寝ることで、背中全体を均等に支えることができます。
膝の下にクッションを置くと、腰への負担を軽減できます。
- 横向きで寝る: 脚を軽く曲げ、膝と肩の位置が自然に保たれるようにします。
肩の下にサポートを提供する枕を使用しましょう。
これらの対策を実践することで、巻き肩や猫背を改善し、より健康的な姿勢を手に入れることができます。
日常生活に取り入れながら、姿勢の改善に努めてみてください。
まとめ
巻き肩や猫背は、筋肉の使い方や寝方によって引き起こされる姿勢の問題です。
これらの姿勢の乱れは肩こりや首の痛み、さらには呼吸や神経系にまで影響を及ぼす可能性があります。
巻き肩や猫背を改善するためには、まずは筋肉バランスを整えるストレッチやエクササイズを取り入れることが重要です。
また、睡眠中の姿勢や寝具の見直しも大切です。
仰向けや横向きでの寝方を意識し、適切なサポートを提供する寝具を選ぶことで、長期的な姿勢の改善が期待できます。
これらの対策を実践し、健康的な姿勢を維持しましょう。
当院では五十肩撃退ブログを執筆しております!
肩の痛みで辛い思いをしている方向けに、五十肩の知識やストレッチなどの改善方法を紹介しています。
人気記事
肩甲骨まわりの筋肉がピクピクする原因は?痙攣は危険信号かも?
腕がピクピクする原因は?痛みがなくても注意するべきポイントを解説!
五十肩にロキソニンは効果ある?痛み止めとして飲み続けて大丈夫?