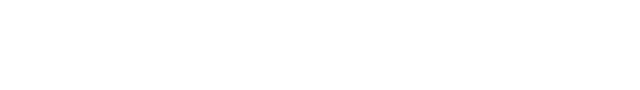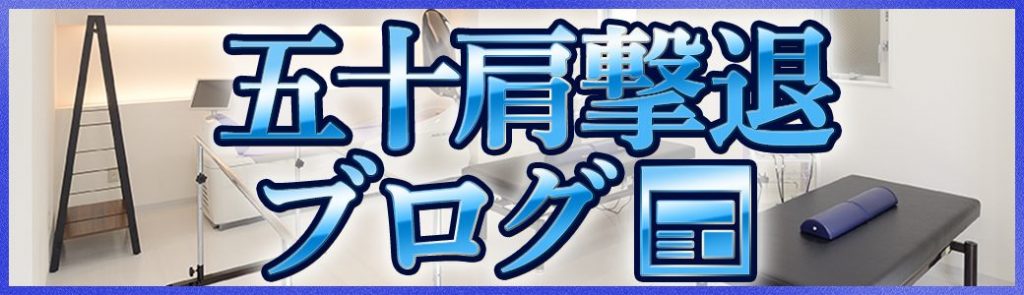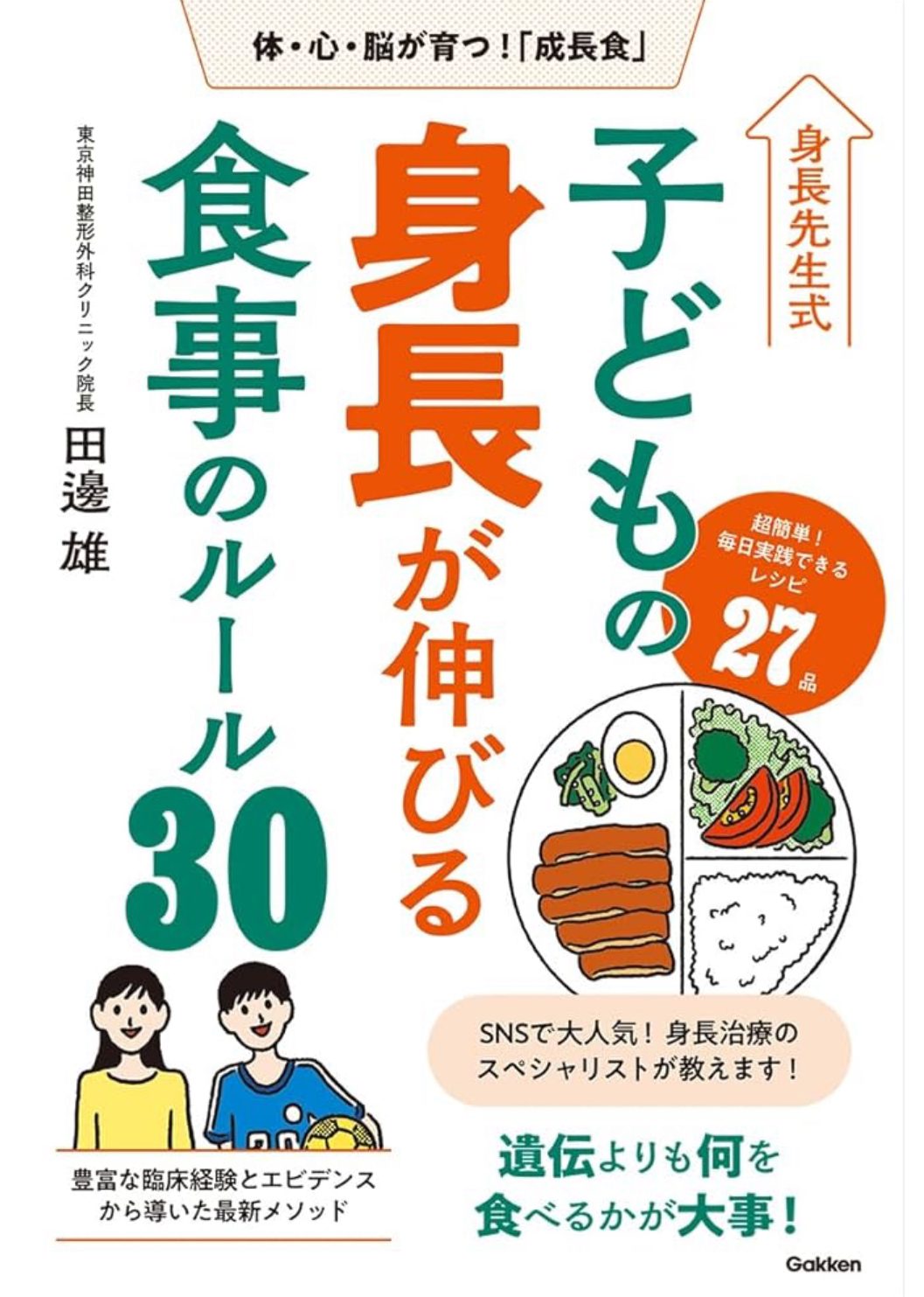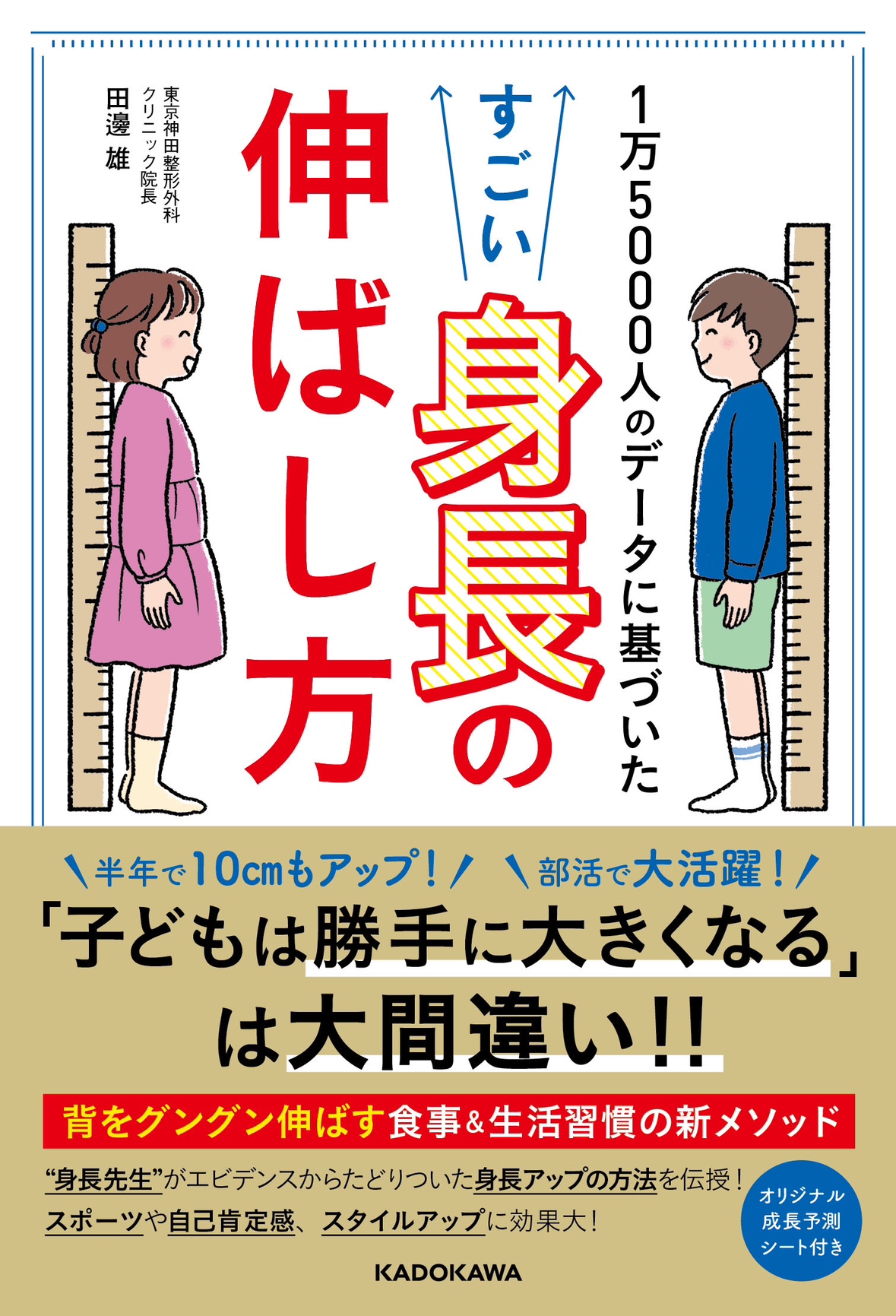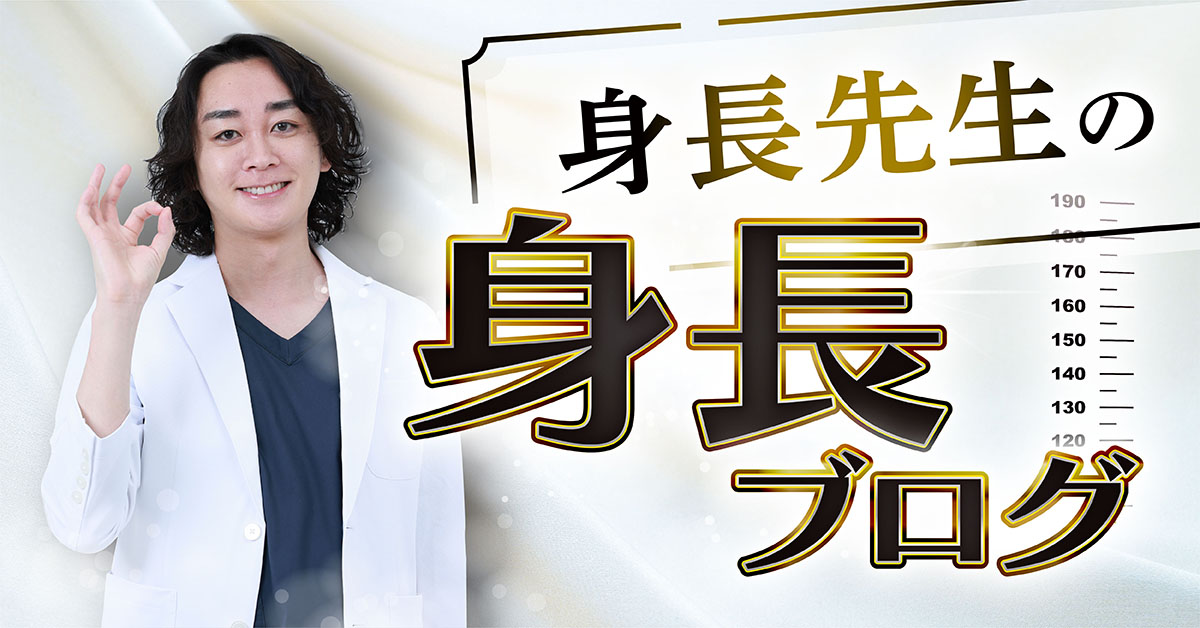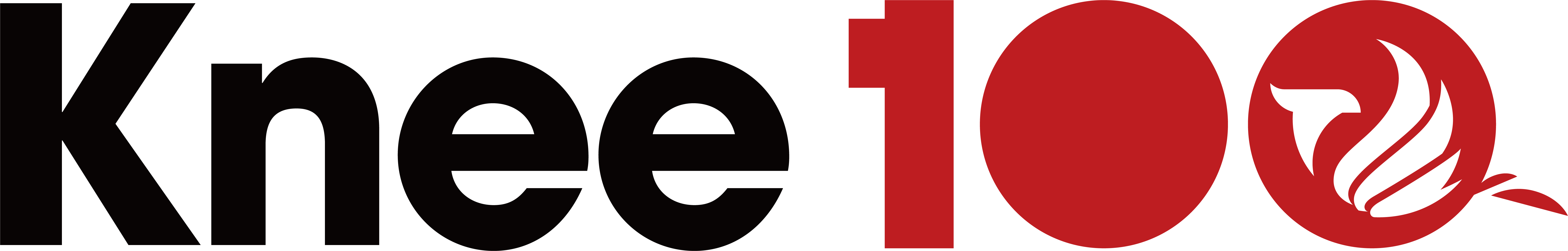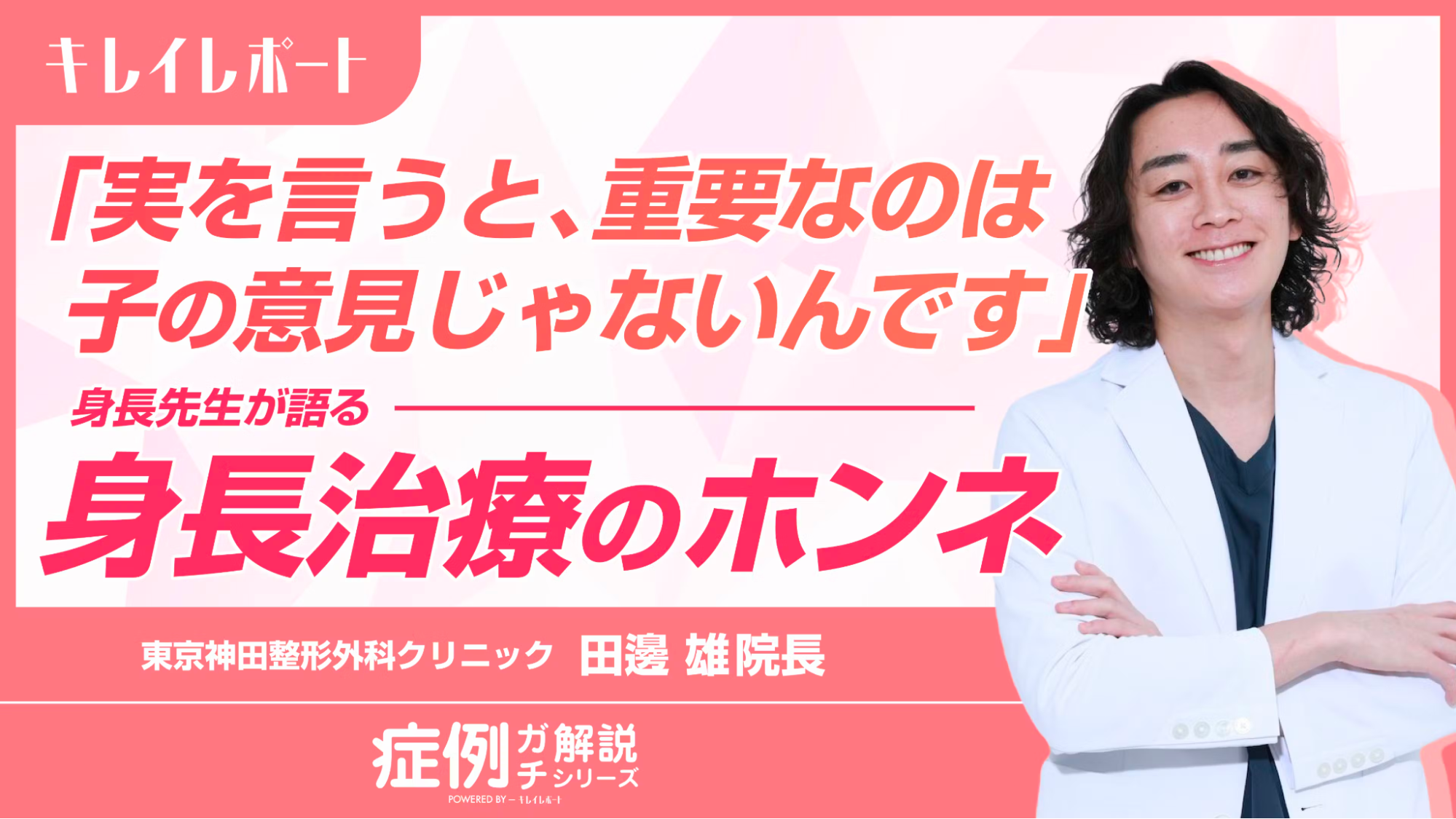肩の可動域が狭くなる原因と解決策:痛みを和らげる方法とは
日常生活において、肩が動かしにくい、可動域が狭いと感じることはありませんか?
そんな方に対し、この記事では、肩の可動域が狭くなる原因や解決策を記しています。
ストレッチなどを使い、痛みを和らげて日常生活での肩の問題を改善して行きましょう。
目次
肩の可動域が狭くなる主な原因

肩の可動域が狭くなる主な原因は、3つあります。
1.加齢による筋力低下と関節の硬直
2.過去の外傷や手術による影響
3.悪い姿勢や生活習慣による負担
では、1つずつ解説していきます。
1.加齢による筋力低下と関節の硬直
肩の可動域が狭くなる主な原因の1つ目は、加齢による筋力低下と関節の硬直です。
加齢により筋力低下や関節の硬直が起こると、肩の可動域は狭くなります。
筋力の低下では、肩を動かすのに必要な筋肉が減ります。
軟骨のすり減りや関節内を満たす滑液が減少することで、関節は硬直します。
2.過去の外傷や手術による影響
肩の可動域が狭くなる主な原因の2つ目は、過去の外傷や手術による影響です。
外傷や手術により長い間肩を動かさずにいると、関節周囲の筋肉や靱帯が硬くなります。
その結果、肩の可動域は狭くなります。
3.悪い姿勢や生活習慣による負担
肩の可動域が狭くなる主な原因の3つ目は、悪い姿勢や生活習慣による負担です。
悪い姿勢や生活習慣による負担は、筋肉が緊張し、硬くなってしまう要因となります。
筋肉が硬くなると関節の動きが制限されてしまうため、肩の可動域は狭くなります。
可動域が狭くなる症状の診断方法

診断は整形外科など、専門医がいる医療機関で診断されます。
問診や視診をはじめ、レントゲンやMRIで骨や筋肉を撮影した画像から診断されます。
肩の可動域を改善させるための具体的な方法

肩の可動域を改善させるための具体的な方法を紹介します。
1.リハビリとストレッチ
2.手術とその後のケア
3.日常的なストレッチとエクササイズ
の3点が重要になります。
1.リハビリとストレッチ
肩の可動域を改善させる具体的な方法の1つ目は、リハビリとストレッチです。
肩の可動域の回復・悪化の予防を行うリハビリとストレッチは重要です。
リハビリとストレッチの効果は、筋肉を硬くしてしまう悪い姿勢や生活習慣の改善を行います。
すでに硬くなってしまった筋肉は、関節や靱帯に負担をかけてしまいます。
そのため、リハビリやストレッチで柔らかくし可動域改善を図るのが重要です。
2.手術とその後のケア
肩の可動域を改善させる具体的な方法の2つ目は、手術とその後のケアです。
リハビリをしても良くならない場合は手術を行います。
手術では、損傷している筋肉の修復や人工関節置換術が行われます。
術後のケアでは、早期に動きの回復が求められます。
組織の修復期間が必要であるため、最初から肩を完全に動かすことはできません。
医師や理学療法士の指示のもと、徐々に可動域を広げる軽い運動やストレッチを行うことが推奨されています。
また、手術後の回復をサポートするには、適切な栄養管理や休養も重要です。
3.日常的なストレッチとエクササイズ
肩の可動域を改善させる具体的な方法の3つ目は、日常的なストレッチとエクササイズです。
タオルストレッチ
肩甲骨周りや肩関節の動きを改善する効果があります。
- タオルを用意し、片手でタオルの一端を持ち、頭の上から背中に垂らします。
- 反対の手でタオルの下端を持ち、両手でタオルを引っ張り合います。
- 背中を伸ばすように意識し、無理のない範囲で30秒キープします。
※反対側も同様に行います。
ポイント: 無理に引っ張りすぎず、心地よい伸びを感じながら行いましょう。
ドアフレームストレッチ
胸筋や前肩を伸ばすことで肩の可動域を広げ、姿勢改善にも役立ちます。
デスクワークやスマホの使用で肩が前にすぼむことが多い方におすすめです。
- ドアのフレームに両手をかけ、肘を90度に曲げます。
- 一歩前に踏み出し、胸を開くようにして前に進みます。
- 肩の前面や胸が心地よく伸びているのを感じながら、15〜30秒キープします。
ポイント: 無理に押し出さず、痛みを感じない範囲で行いましょう。
リラックスした呼吸を続けることが大切です。
肩の可動域を保つための日常生活の注意点
肩の可動域を保つための日常生活の注意点は、2つあります。
1.正しい姿勢の維持
2.定期的な運動と生活習慣の改善
どのように注意したらいいのかを1つずつ説明していきます。
1.正しい姿勢の維持
肩の可動域を保つための日常生活の注意点の1つ目は、正しい姿勢の維持です。
正しい姿勢とは、体を横から見たときに耳・肩・骨盤が一直線上に並んでいる状態です。
この姿勢をとることで、肩甲骨や肩関節が正しい位置で働くことができます。
肩をリラックスさせることも重要です。
肩に力が入りすぎていると、肩回りの筋肉が緊張し動きが制限されてしまいます。
肩甲骨を引き寄せるように、かつ、肩が上がらないようにしましょう。
正しい姿勢を維持するには、姿勢に意識を向けて良い姿勢の時間を増やしていくことです。
デスクワークやスマートフォンを操作しているとき、肩がすくんでいませんか?
気付いたときに良い姿勢に戻していきましょう。
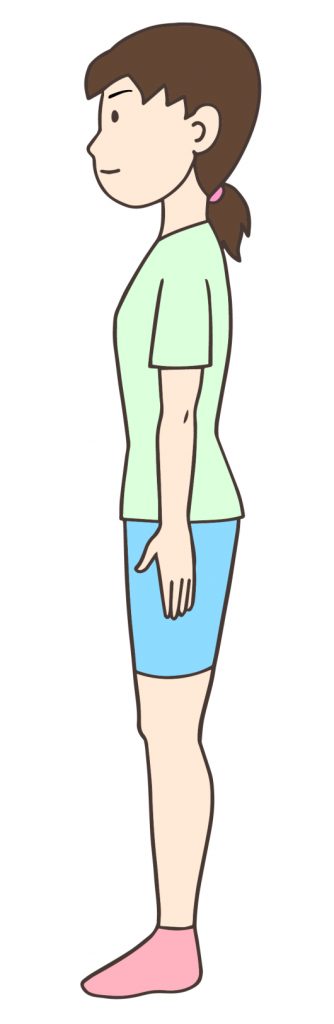
2.定期的な運動と生活習慣の改善
肩の可動域を保つための日常生活の注意点の2つ目は、定期的な運動と生活習慣の改善です。
肩の動きが悪くなってしまう原因には、筋肉が固まってしまうことが挙げられます。
定期的な運動を行い、筋肉が固まるのを防ぎましょう。
生活習慣の改善は、肩に負担をかけないために欠かせません。
まずは正しい姿勢をとることが基本となりますが、やはりずっとは難しいです。
長時間同じ姿勢をとらないように注意し、気付いたときに良い姿勢に戻しましょう。
症状が悪化した場合の対処法

悪化した場合は、行っている運動やストレッチは中止しましょう。
痛みが続く場合や肩の可動域が低下した場合は、早めに受診することをおすすめします。
炎症が強い場合はアイシングをしたり、痛み止めを処方してもらいましょう。
まとめ
以上、肩の可動域が狭くなる原因と対処法でした。
肩の可動域が狭くなる主な原因は、
- 加齢による筋力低下
- 過去の外傷や手術
- 悪い姿勢や生活習慣
がありました。
これらが筋肉や関節を硬くし、肩の動きを制限します。
改善にはリハビリやストレッチが有効です。
さらに正しい姿勢の維持と日常的なエクササイズも重要となります。
肩の可動域を守るためには無理せず定期的に運動を行いましょう。
悪化した場合は早めに専門医を受診しましょう。
当院では五十肩撃退ブログを執筆しております!
肩の痛みで辛い思いをしている方向けに、五十肩の知識やストレッチなどの改善方法を紹介しています。
人気記事
肩甲骨まわりの筋肉がピクピクする原因は?痙攣は危険信号かも?
腕がピクピクする原因は?痛みがなくても注意するべきポイントを解説!
五十肩にロキソニンは効果ある?痛み止めとして飲み続けて大丈夫?