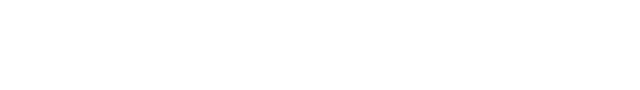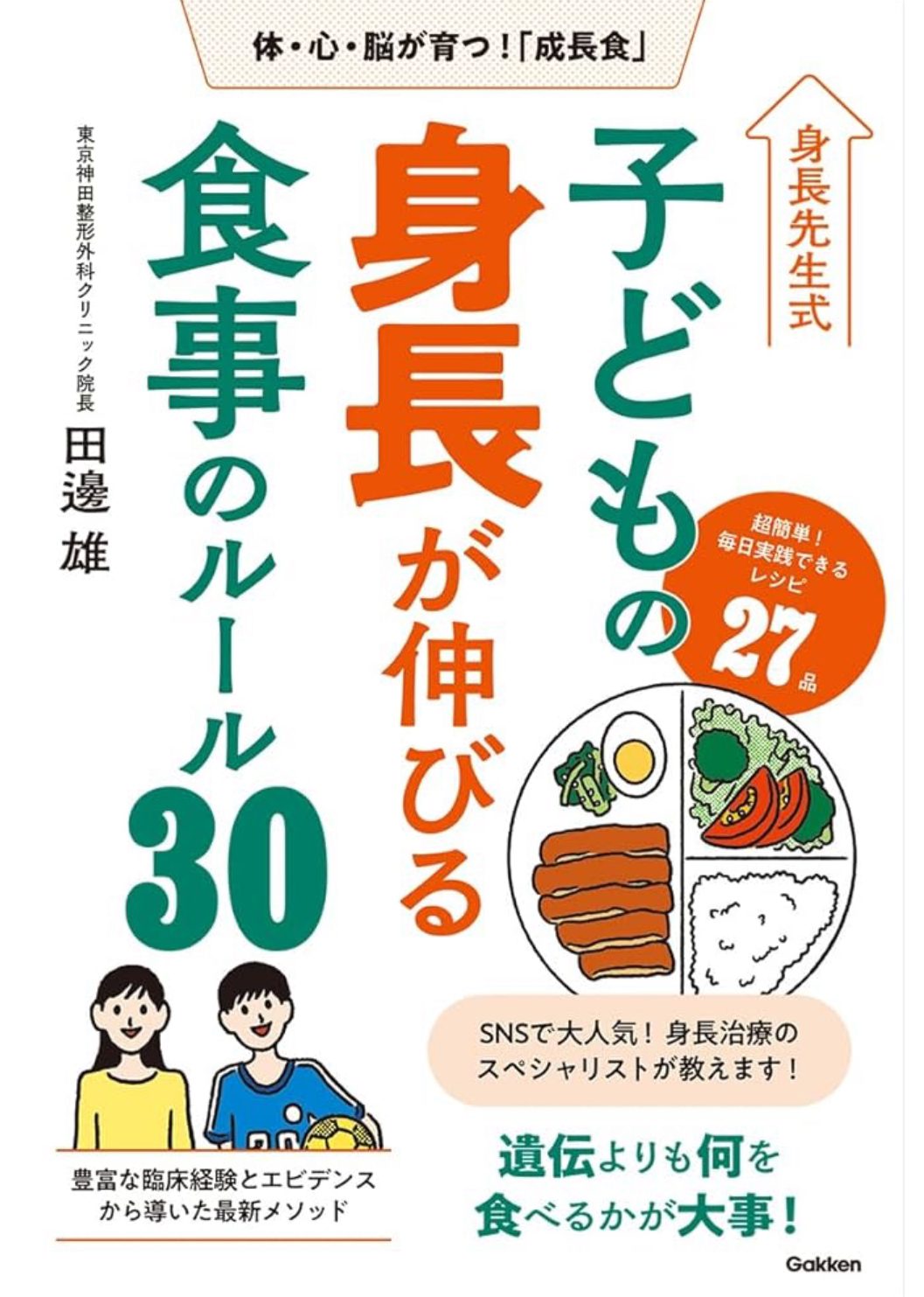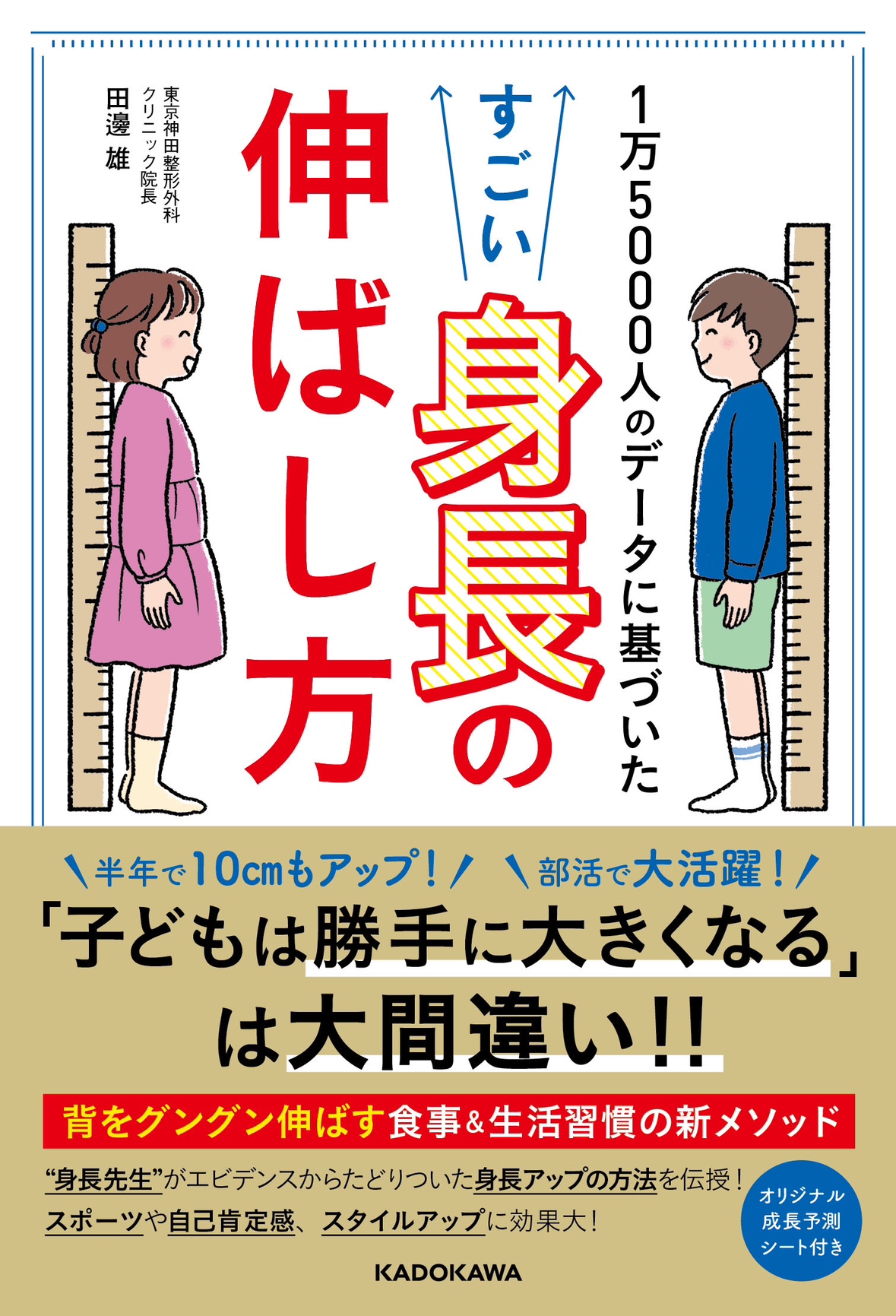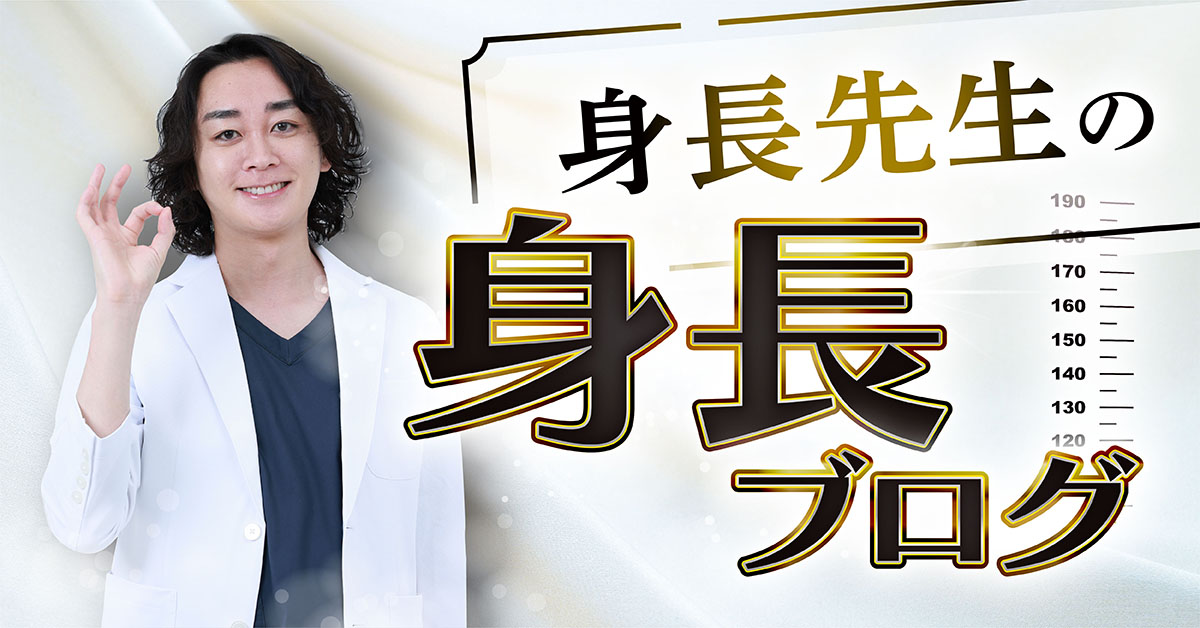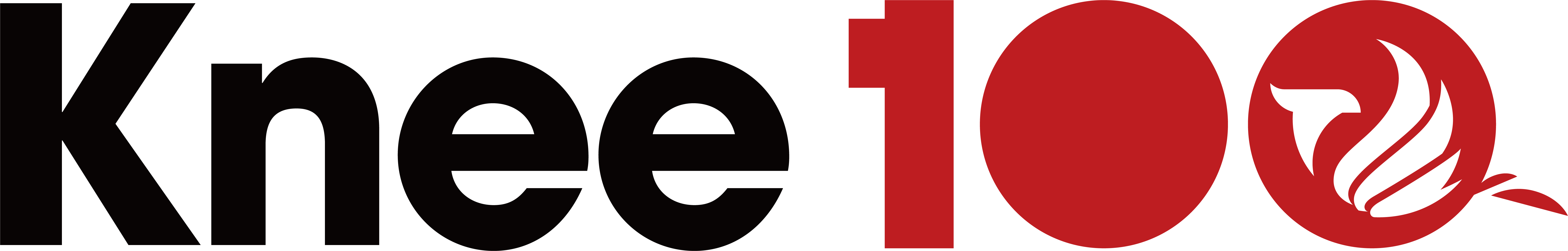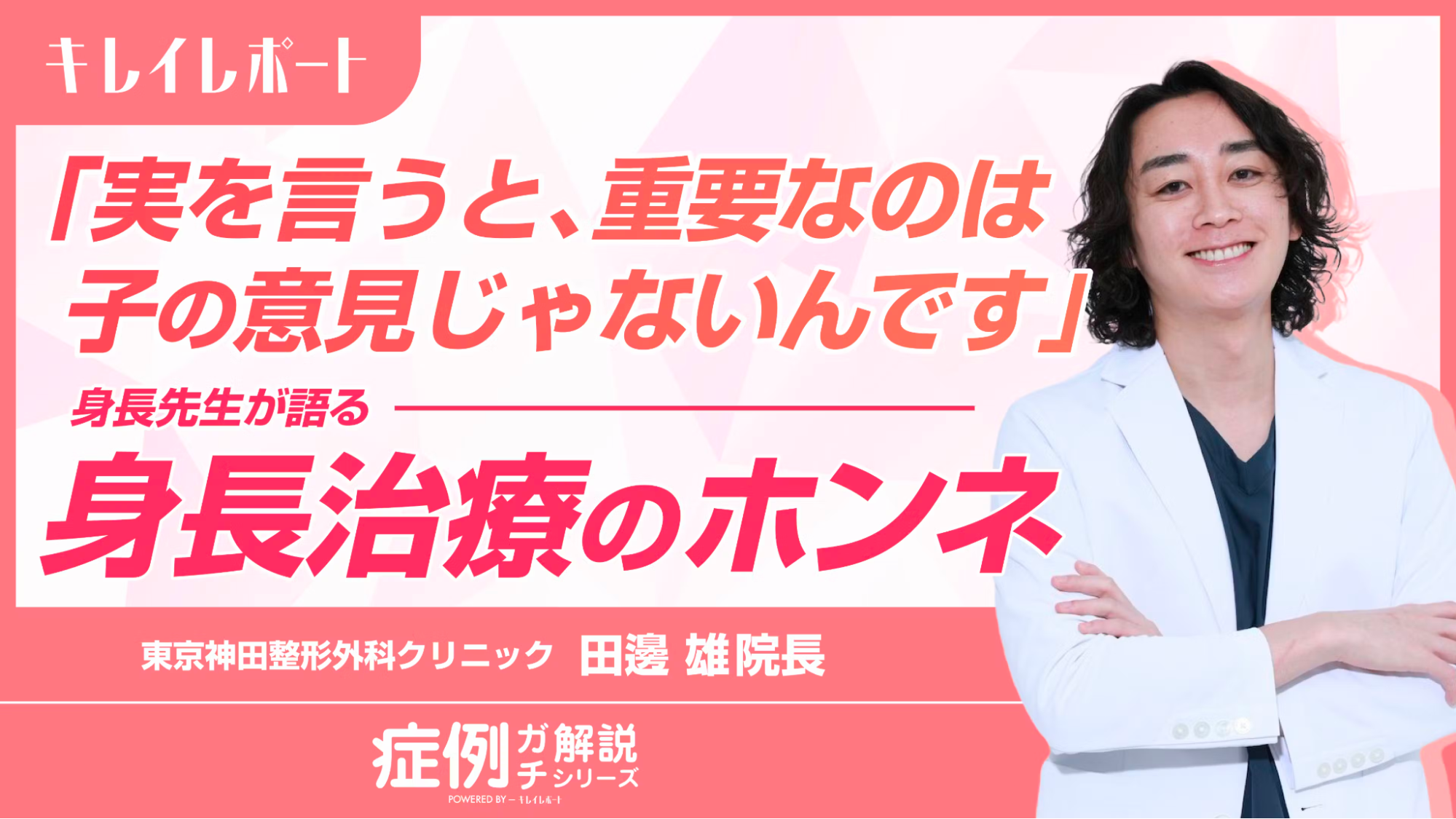五十肩とは?原因や要因に治療期間の平均など詳しく解説!
【疑問解決】五十肩とは何ぞや?【知識編】
東京神田整形外科クリニック、院長の田邊こと、ベンベン先生です!
今回のテーマは、五十肩とは何ぞや?という内容でお話していきます。
五十肩とは何ぞや?
整形外科では50歳前後で起こる方の痛み・運動障害を、大まかに肩関節周囲炎という風に言います。
これをさらに細分化したものが
・滑液包炎
・上腕二頭筋腱炎
・石灰化沈着
・腱板損傷
この4つになります。
それをさらに大衆化したものを、一般的に「五十肩」という風に言われています。
「四十肩」というのもよく巷では聞くと思いますが、それと全く同じものです。
当然60代・70代でもあり得ますし、30代の方というのもいらっしゃいます。
「概ね50歳前後で起きやすい肩の痛みや運動障害」=五十肩
五十肩の歴史について
江戸時代の広辞苑的な書物にも「五十肩」というのは記載があります。
その頃から一般的に使われていた言葉だという風に言われています。
現代ではおよそ600万人、五十肩の方がいると言われています。
その割に一般化されたのは江戸時代というのは、ちょっと遅い気がしませんか?
これには平均寿命が大きく関係しています。
江戸時代は大体30〜40代が平均寿命と言われています。
それ以前の戦国時代などは、さらに短かったと考えられます。
織田信長の有名な口上で「人間五十年」という言葉ありますが、このときは50年よりはもっと短い寿命で亡くなってしまう方がたくさんいたという風に言われています。
つまり、50歳まで生きる人がそんなにいなければ五十肩になることはないということですね。
そういった意味で、江戸時代ぐらいから大体50歳以上まで生きる人が増えてきたということで、一般化してきた言葉が「五十肩」ということになると思います。
五十肩の原因
ここまで話しましたけれども、五十肩になる原因というのははっきり分かっておりません。
おいっ!と思う方もいらっしゃると思いますが、なぜ原因が分からないのかとか、現在分かっていることというのを、私の知見も合わせてお話しさせていただきます。
まず50歳前後で起きるということで、年齢が大きく関係しているのが分かると思いますが、その原因を追求しようと考えたときに、10代とか若い人が大体50歳になって、実際に五十肩を発症するまでの人たちを追いかけないといけないんです。
この追いかけた人も1人2人では当然ダメで、なおかつ気の遠くなるような人数のデータを集めて解析をしないと、おそらくその原因というのが分からないと思うんです。
これは全然現実的なことでなく、非現実的な量のデータが必要になるため、原因ははっきり分かっていないのです。
肩関節の機能(メリット)
肩関節を考えた時に、構造は上腕骨が鎖骨・肩甲骨に収まって構成されています。
その間を筋肉・靭帯が結びついてつながって、肩関節を作っているわけです。
体の他の大きな関節と違うのは、肩関節はとても自由度が大きいという事です。
自由度というのは、可動域とか動きの意味ですね。
このルーツをたどってさらに昔にさかのぼりますと、人類というのは4足歩行からだんだん2足歩行になっていきます。
この自由になった前足というのが、私達の腕・肩になるわけです。
腕が自由に使えるようになったことで、木の上の高いものを取ることができたり、石を投げたりして狩猟したり、そういうことができるようになったわけですね。
このように肩関節は「球関節」とも言われていて、肩関節は非常に大きな自由度と多彩な可動域を持っています。
実際に前後もそうですし、左右や内・外の動きだったりひねったりする動きが可能となっています。
このように動く関節というのは、体の中でも他にはありません。
加えて現代野球で言いますと、例えば肩を使って160km/hの球を投げることもできたり、バーベルのデッドリフトという下から持ち上げるバーベルの世界記録は約500kgと、とにかく体重の3〜4倍ぐらいは優に持てるぐらいのパワーを持っています。
このように、広い可動域とパワーを両立させているのが肩関節のすごいところです。
肩関節の機能(デメリット)
決して良いことばかりではなくて、大きな可動性があるということは、裏を返せば不安定であるということも言えます。
前述した通り、肩というのは上腕骨が肩甲骨・鎖骨に収まってできています。
なので骨としてはつながりがないので、ぶら下がったような構造なんですね。
肩関節は靭帯・筋肉によって支えられているということです。
ということは、肩の筋肉には一定の力がずっとかかり続けているということになります。
これは短期間ではあまり大した問題ではないのですが、すごく長い時間、特に50年単位とかになった時に、筋肉・靭帯を痛めてしまったり、炎症を起こしてしまったりということが起因して五十肩になってしまうわけですね。
五十肩の治療期間の平均・予後に関連する要因
先程ご説明した多彩なパワー・可動域というのは本来相反するものなので、この2つを発揮できる肩関節、これを制御する機構というのはすごく複雑です。
その複雑さゆえに五十肩になってしまってバランスが崩れた時に、元に戻すのは大変と言われています。
様々な論文ベースで見ましても、大体半年・1年、長いものだと2年と書いてある論文もあったりして、やっぱり五十肩の治療が長引くというのはそういったところから言えることです。
これに加えて生活習慣ですね。
特に姿勢が悪かったり、あとは腕や肩を酷使する仕事をしている場合にも、当然増悪する因子になりやすいです。
あとは基礎疾患ですね。
糖尿病・内分泌系の疾患を持っていると、これも増悪の因子になりやすいと言われています。
また、心因性のストレスも増悪する因子の1つになるかと思います。
五十肩の問題
続いて五十肩の問題についてです。
症状が発症してから大体来院するまでに2〜3ヶ月というのが一般的に言われています。
2〜3ヶ月経った時点で来院した五十肩というのは、ものすごく周りの組織が硬くなっています。
先程お伝えした方の制御系も、硬い・制御系がめちゃくちゃに狂っているということで、とても治療が大変です。
明らかに、発症してから早く治療した方は治りが良いです。
ですので、「今現在症状があるよ」という方は、ぜひ東京神田整形外科クリニックに受診していただけると、リハビリを担当する側としてはとてもありがたいです。
動かなくなる前に来て下さい!
まとめ
以上、五十肩について解説させていただきました。
いかがだったでしょうか。
もし五十肩のリハビリをご希望の際は、田邊をご指名下さい。
このご時世で「遠くて行けないよ」という方は、YouTubeチャンネルでも五十肩について配信していますので、チャンネル登録をして、五十肩の予防・治療の運動を一緒にしていきましょう!
世の中の五十肩で悩む人の役に立ち、少しでも解決できるようにこれからも務めさせていただきます。
院長の田邊こと、ベンベン先生でした!