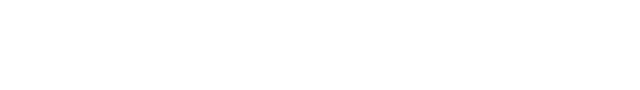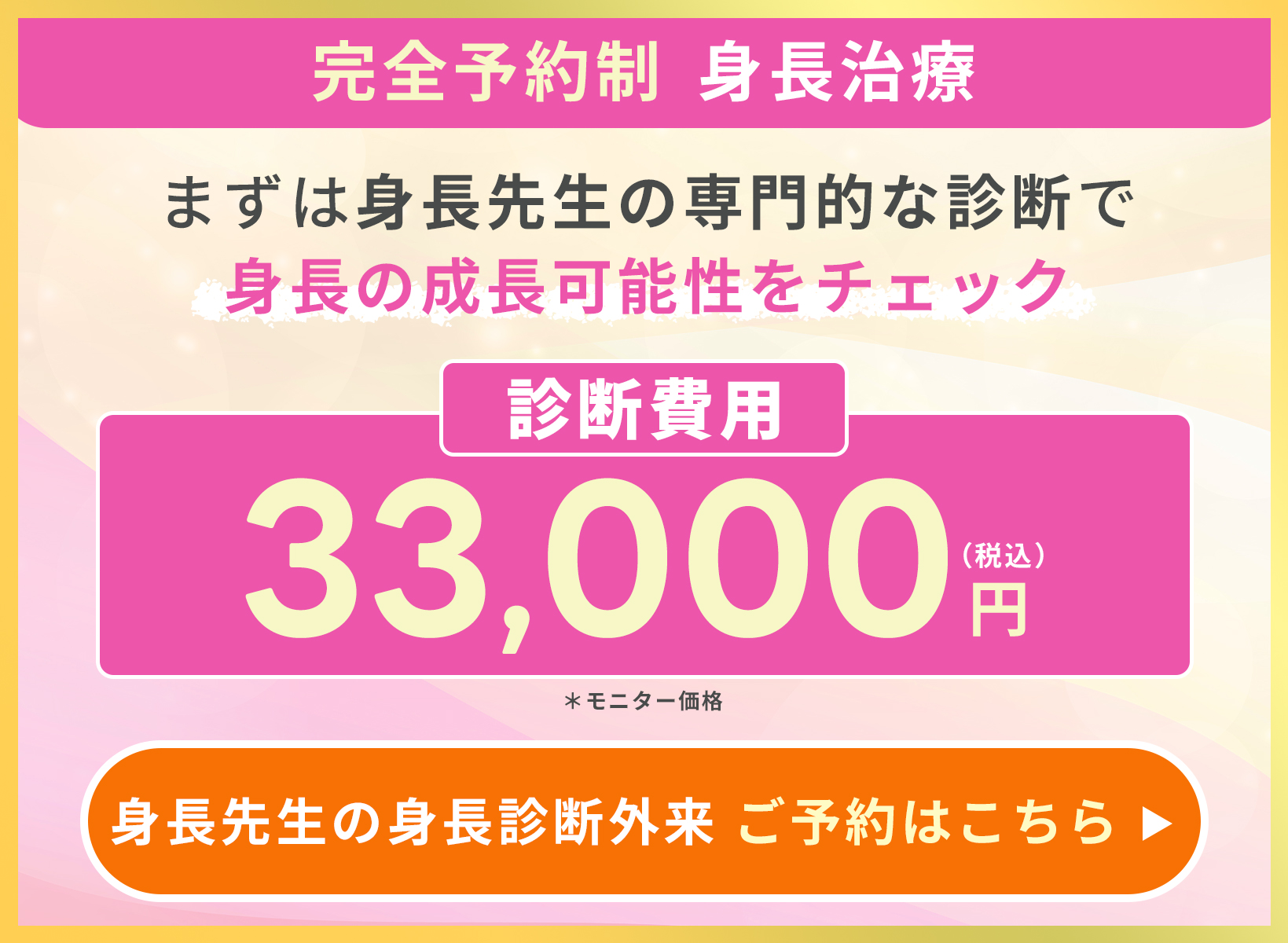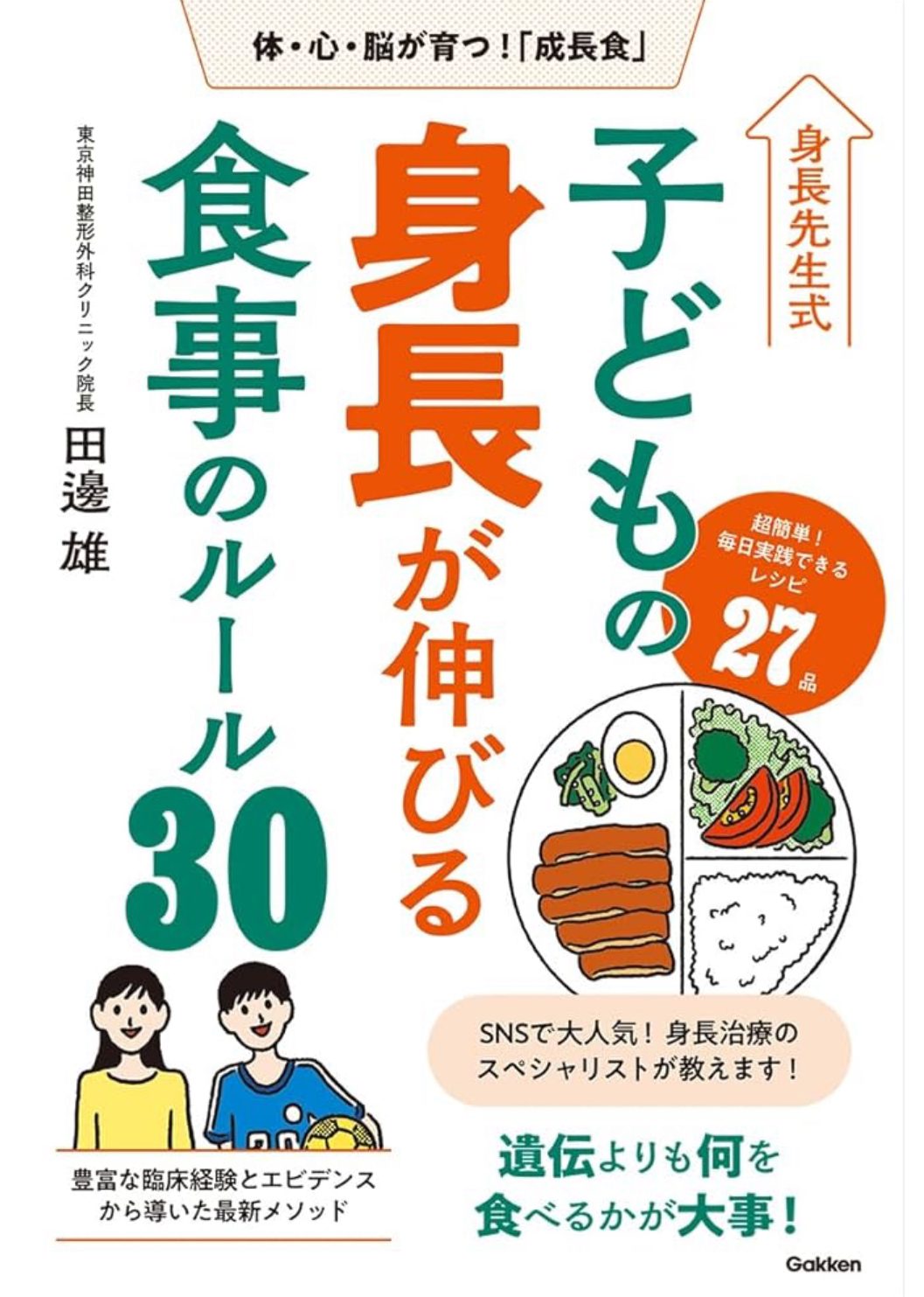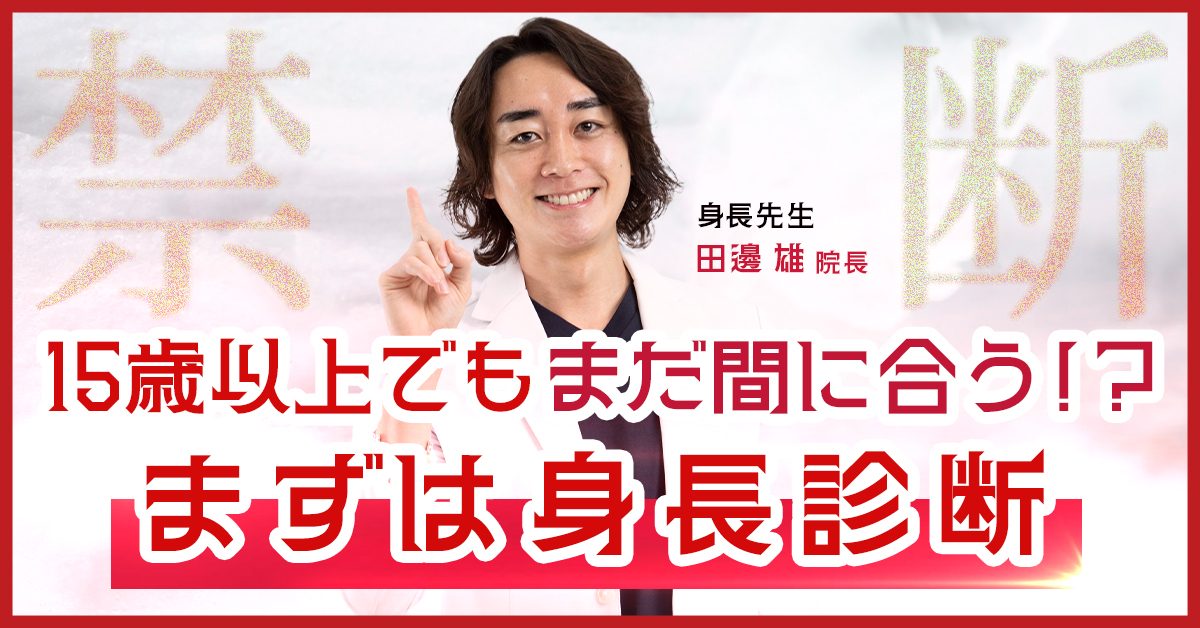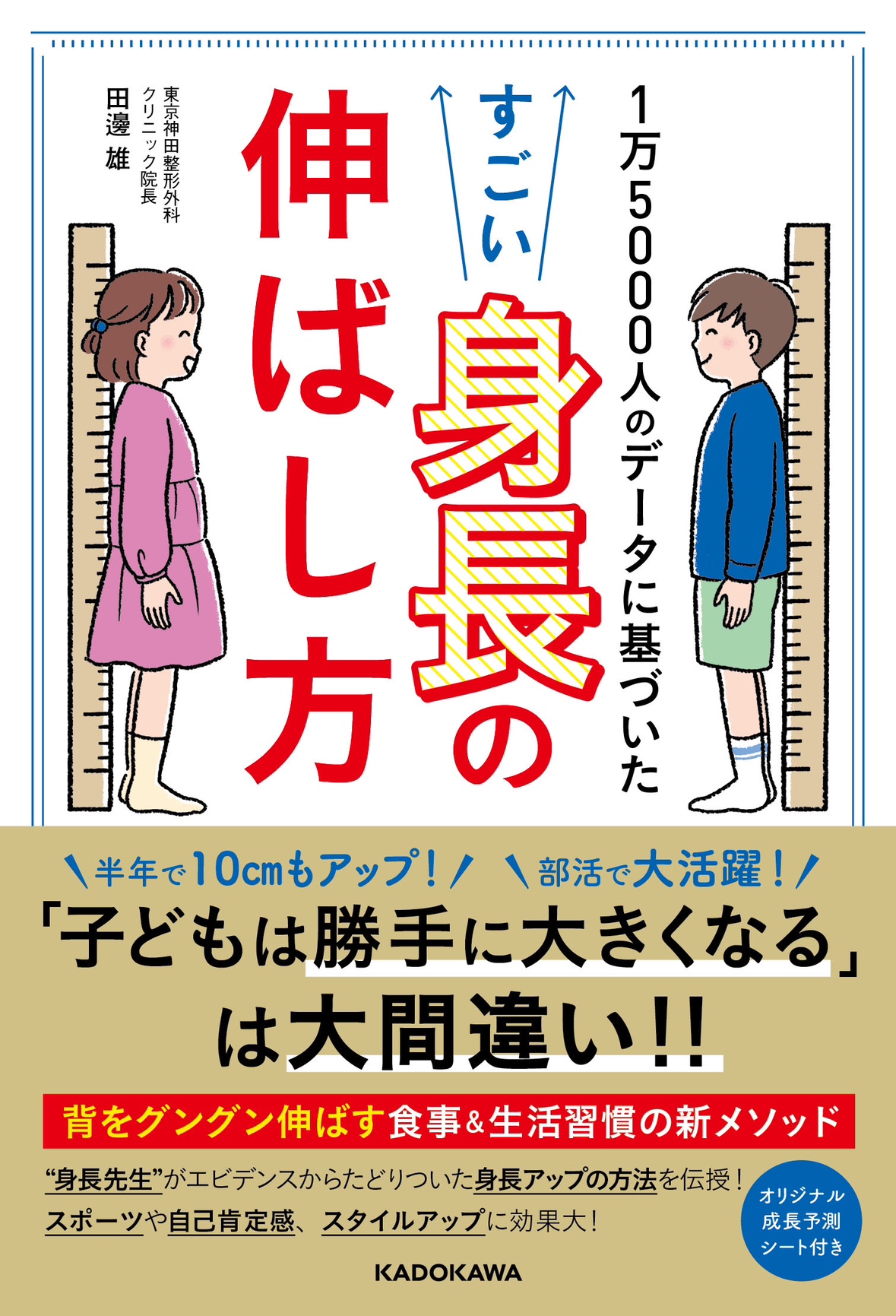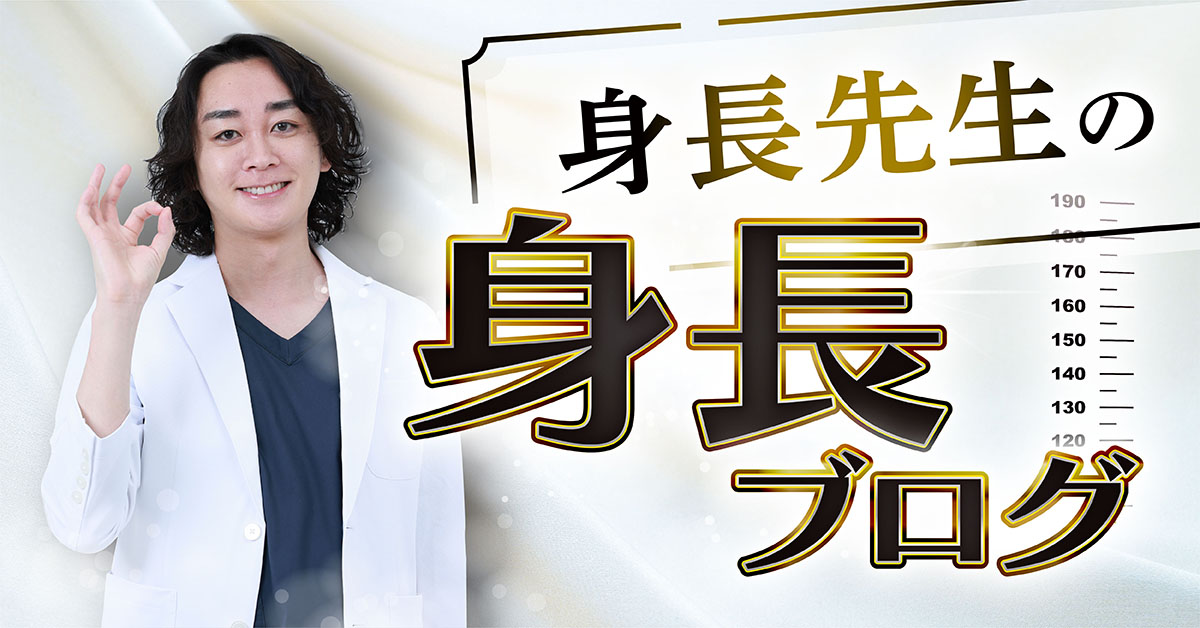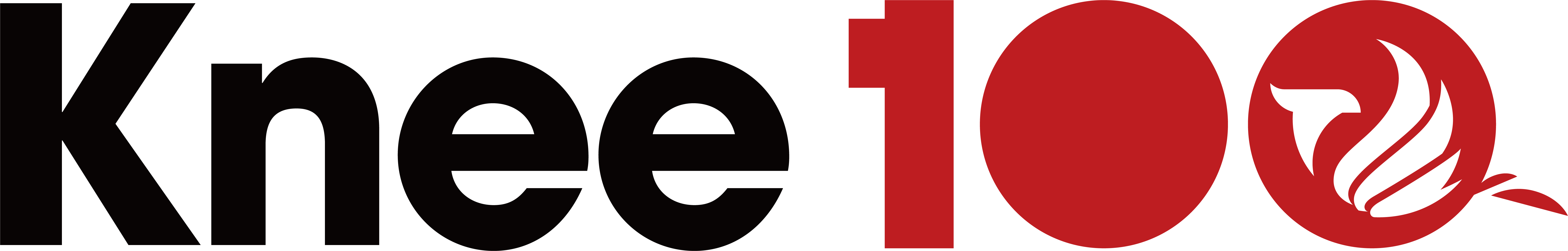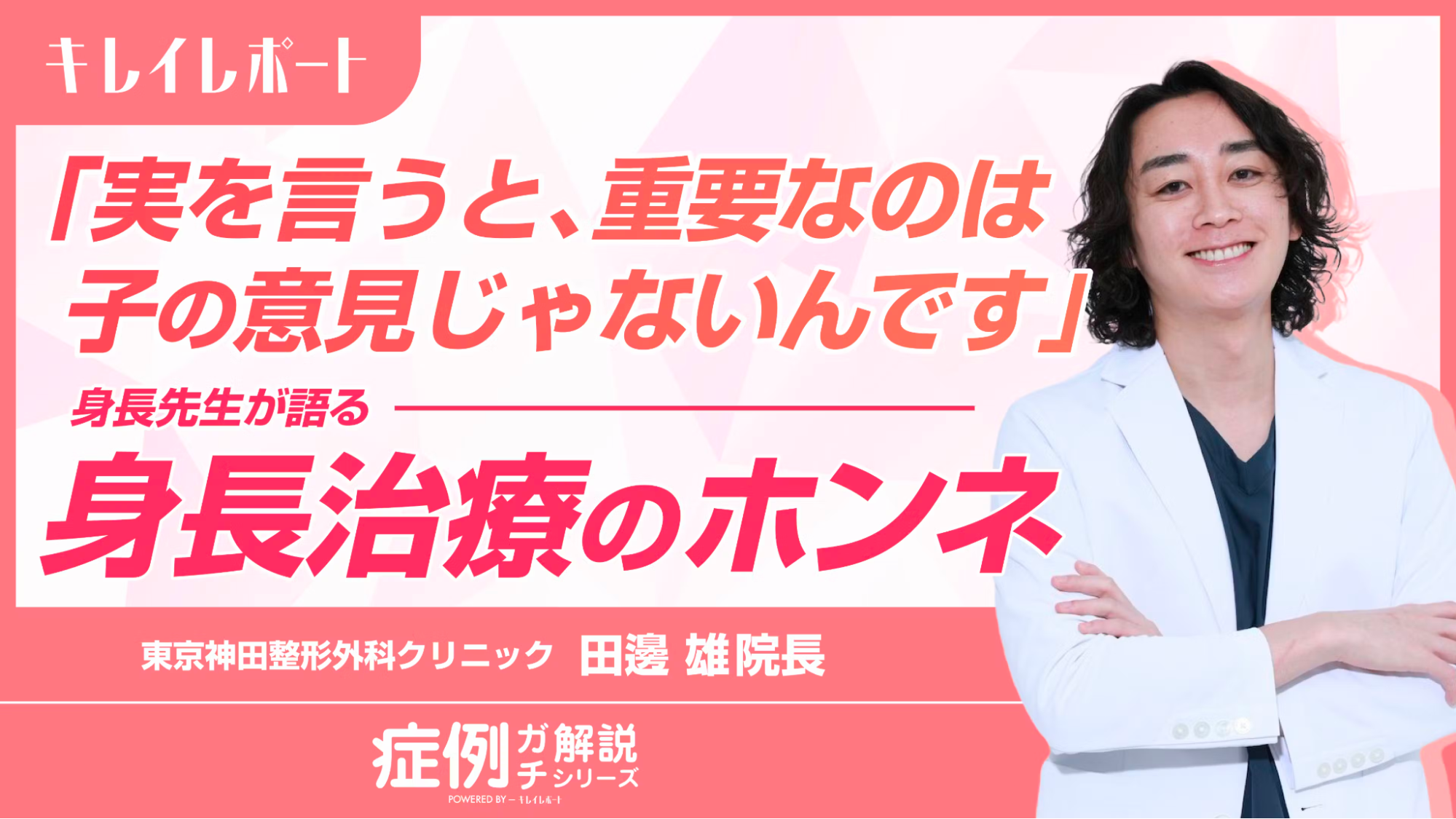1歳の月齢別平均身長を男女ごとに紹介!身長が伸びないときの原因と治療法 | 低身長治療・再生医療なら東京神田整形外科クリニック

「1歳の子どもの身長が周囲の子と比較して小さい」「この先身長を伸ばしていくためにできることを知りたい」
1歳児のお子さんの身長が小さいとき、周囲のお子さんと比較をして不安な気持ちを抱えられているかもしれません。
お子さんの成長スピードは、さまざまなので、心配しすぎる必要はありません。ただ、この先も伸び悩むときのための、解決方法も知っておくことが大切です。
この記事では、1歳児の月齢別平均身長(男女別)に加え、身長が伸びにくい原因や、ご家庭でこの先できる対策を解説します。
1歳子どもの平均身長を月齢別に紹介【男の子・女の子】

1歳児の平均身長は、月齢によって変化します。
男の子と女の子で平均身長が異なるため、それぞれ月齢別に分けて解説します。
1歳の男の子の平均身長
|
月齢 |
平均身長 (cm) |
標準偏差 (cm) |
-2SD (cm) |
-2.5SD (cm) |
|---|---|---|---|---|
|
0ヶ月 |
75.0 |
2.6 |
69.8 |
68.5 |
|
1ヶ月 |
76.0 |
2.6 |
70.8 |
69.5 |
|
2ヶ月 |
76.9 |
2.6 |
71.6 |
70.3 |
|
3ヶ月 |
77.8 |
2.7 |
72.5 |
71.1 |
|
4ヶ月 |
78.7 |
2.7 |
73.3 |
71.9 |
|
5ヶ月 |
79.6 |
2.8 |
74.1 |
72.7 |
|
6ヶ月 |
80.5 |
2.8 |
74.9 |
73.5 |
|
7ヶ月 |
81.4 |
2.8 |
75.7 |
74.3 |
|
8ヶ月 |
82.3 |
2.9 |
76.5 |
75.1 |
|
9ヶ月 |
83.1 |
2.9 |
77.3 |
75.8 |
|
10ヶ月 |
83.9 |
2.9 |
78.0 |
76.6 |
|
11ヶ月 |
84.7 |
3.0 |
78.7 |
77.2 |
1歳の女の子の平均身長
|
月齢 |
平均身長 (cm) |
標準偏差 (cm) |
-2SD (cm) |
-2.5SD (cm) |
|---|---|---|---|---|
|
0ヶ月 |
73.4 |
2.5 |
68.4 |
67.1 |
|
1ヶ月 |
74.5 |
2.5 |
69.4 |
68.1 |
|
2ヶ月 |
75.5 |
2.6 |
70.3 |
69.0 |
|
3ヶ月 |
76.5 |
2.6 |
71.3 |
70.0 |
|
4ヶ月 |
77.5 |
2.6 |
72.2 |
70.8 |
|
5ヶ月 |
78.4 |
2.7 |
73.0 |
71.7 |
|
6ヶ月 |
79.4 |
2.7 |
73.9 |
72.5 |
|
7ヶ月 |
80.3 |
2.8 |
74.7 |
73.4 |
|
8ヶ月 |
81.2 |
2.8 |
75.6 |
74.2 |
|
9ヶ月 |
82.0 |
2.8 |
76.3 |
74.9 |
|
10ヶ月 |
82.8 |
2.9 |
77.1 |
75.6 |
|
11ヶ月 |
83.5 |
2.9 |
77.7 |
76.3 |
1歳の子どもの成長の特徴とは
1歳の子どもの成長には、身体的発達、精神的発達、社会性発達など、様々な側面があります。
この時期の子どもは、歩けるようになったり、言葉を話し始めたりと、目覚ましい成長を遂げることが特徴です。
さらに、周囲の人々との関わりの中で、社会性を身につけていく時期でもあります。
時期に合わせた適切なサポートをすることが重要であるため、それぞれの発達段階の成長の特徴について理解を深めましょう。
1歳の子どもの成長
1歳になると、身長の伸びは新生児期や乳児期と比べて緩やかになります。
生後1年間で約25cmほど伸びた後、1歳から4歳頃までは年間7〜10cm程度のペース(1〜2歳で約10cm、2〜3歳で約8cm、3〜4歳で約7cmが目安)で伸びていき、その後思春期を迎えるまで緩やかな成長が続きます。
また、1歳は赤ちゃん期から幼児期への移行期間にあたります。
身長の伸びだけでなく、歩く、話すといった発達も大きく進む時期です。
つかまり立ちや伝い歩きから、一人で歩けるようになる子も増え、行動範囲が広がります。
言葉では、喃語から単語を話し始めるようになり、親とのコミュニケーションも活発になります。
もちろん、成長には個人差があるため、その点を理解しながら、栄養や生活習慣を整えてあげることが大切です。
子どもの成長の特徴とは
子どもの身長がどのように伸びていくのか、一般的なパターンを知っておきましょう。
まず、生まれてから1歳までの1年間は、人生で最も身長が伸びると言われています。
出生時の身長は約50cmですが、この1年間で約25cmも伸び、1歳になる頃には約75cmと、なんと1.5倍近くまで成長します。
1歳を過ぎると、身長の伸びるペースは少し緩やかになります。
- 1歳〜2歳:年間約10cm
- 2歳〜3歳:年間約8cm
- 3歳〜4歳:年間約7cm
このように伸びていき、4歳になる頃には約100cmに達するのが一つの目安です。
その後、思春期の前までは緩やかな伸びが続きますが、思春期を迎えると再び身長がぐんと伸びる時期、「成長スパート」が訪れます。
個人差はありますが、一般的に男の子は12歳から14歳頃に年間約10cm、女の子は10歳から12歳頃に年間約8cm程度、身長が大きく伸びます。
もちろん、子どもの成長には個人差があり、発達のスピードや順序は一人ひとり異なります。
ここで紹介した数値はあくまで一般的な目安です。
発達段階の特徴を理解しつつ、子どものペースに合わせて見守ることが重要です。焦らず、比較せずに、子どもの成長を温かくサポートすることで、健やかな発達を促すことができます。
また、定期的な健康診断や育児相談などを活用し、専門家からアドバイスを受けつつ見守ることが大切です。
1歳の子どもの身長を今後伸ばすために大切な生活習慣

1歳の子どもの成長を促進していくためには、生活習慣を整えることが重要です。
睡眠、食事、運動の3つのポイントに焦点を当てて、親御さんができることを解説します。
睡眠
睡眠は、成長ホルモンの分泌に大きく関わっています。睡眠時間が不十分だったり、生活が不規則だったりすると、十分な成長ホルモンが分泌されず、成長が妨げられてしまいます。
1歳の幼児であれば、11~14時間の睡眠を確保することが望ましいです。成長期である小学生では、10時間程度の睡眠が必要です。
特に5歳未満の子どもにとって、昼寝は夜の睡眠時間を補うために重要です。
年齢が上がるにつれて昼寝の必要性は減少していきますが、小学生までは昼寝をすることで成長ホルモンの分泌を促進し、身長の伸びをサポートできる可能性があります。
ただし、昼寝が夜の睡眠に悪影響を与える場合は、控えるようにしましょう。
規則正しい生活リズムを心がけ、質の良い睡眠をとれるように環境を整えてあげてください。
食事
バランスの取れた食事は、子どもの成長に欠かせません。
特に身長を伸ばすために重要な栄養素は、タンパク質、カルシウム、ビタミンD、亜鉛、マグネシウムです。
タンパク質は筋肉や骨の成長に、カルシウムは骨を丈夫にするために必須です。ビタミンDはカルシウムの吸収を助け、亜鉛は成長ホルモンの分泌を促します。
また、マグネシウムは骨の形成を助ける役割があります。これらの栄養素をバランスよく含む食材を積極的に取り入れましょう。
運動
バランスの良い食事に加えて、日光浴や適度な運動を組み合わせることで、より健康的な成長を促すことができます。
日光浴をすると、体内でビタミンDが生成されます。ビタミンDはカルシウムの吸収を助け、丈夫な骨を作るために不可欠な栄養素です。骨がしっかりと成長することが身長の伸びにつながるため、適度な日光浴は大切とされています。
また、1歳児であれば、ハイハイや歩く遊びといった、骨に適度な刺激を与える運動が効果的です。全身を使う運動は成長ホルモンの分泌を促すため、積極的に取り入れましょう。
また、親子で楽しめる運動は、継続しやすいというメリットがあります。楽しみながら体を動かす習慣を身につけていきましょう。
身長が伸びない場合の低身長の判断基準と原因
「子どもの身長は順調に伸びているか」「他の子供と比べて小さくないか」
これは、多くの保護者の方が気にされることかもしれません。特に、周りの子と比べて身長が低いように感じると、将来への不安も募るものです。
本章では、低身長の医学的な判断基準と、低身長の原因となる様々な要因について詳しく解説していきます。
お子様の成長について理解を深め、適切な対応につなげるためにぜひ参考にしてください。
低身長と判断される基準
低身長の判断には、統計的な基準が用いられます。
具体的には、身長が同年齢・同性の平均値から-2SD(標準偏差)以下の場合を「低身長」と判断します。この平均身長と標準偏差は、厚生労働省が発表している成長曲線で確認できます。
また、成長速度も重要な指標です。
1歳児であれば、年間の成長速度は約7~10cmです。年間の伸びが5cm未満の場合は、成長が遅れていると判断される可能性があります。
低身長の基準に当てはまる、あるいは成長速度が遅い場合は、一度専門医への相談もご検討ください。
低身長の原因
低身長の原因は多岐に渡り、大きく分けて病気によるものと、病気以外のものがあります。
主な原因を以下に挙げて解説します。
家族性低身長など病気以外のもの
身長の低い方が多い家系のとき、お子さんの身長も低くなることがあります。これは病気ではなく体質的なもので、特別な治療は必要ありません。
また、ご両親の身長が低いからと言って、お子さんの身長が必ずしも低くなるとは限りません。
家系によるもの以外にも、生活習慣の乱れや栄養不足なども原因で、身長が伸びにくくなることがあります。
ホルモンの異常
成長ホルモンは、身長の伸びに大きく関わっており、成長ホルモンの分泌不足が起こると、低身長となる可能性があります。
成長ホルモンは脳の下垂体から分泌され、肝臓や骨の先端部分にある軟骨(骨端軟骨)に働きかけます。これらの場所で作られるのが「成長因子(IGF-I)」と呼ばれる物質です。この成長因子が骨に作用することで骨が長くなり、結果として身長が伸びる仕組みです。
そのため、成長ホルモンの分泌不足があると、低身長となる可能性があります。
その他、甲状腺ホルモンの不足なども成長に影響を及ぼすことがあります。ホルモンの異常が疑われる場合は、血液検査などでホルモン値を調べることを推奨します。
染色体の異常
染色体の異常で起こる代表的な疾患はターナー症候群です。ターナー症候群は、女児にみられる染色体異常で、低身長のほかにも様々な症状が現れます。
染色体異常が原因の低身長の場合、根本的な治療は難しいですが、成長ホルモン療法などで身長を伸ばす治療を行うことができます。
SGA性低身長
出生時の体重や身長が、在胎週数相当の標準値よりも小さい「SGA(Small for Gestational Age)」の場合、その後の成長にも影響を及ぼし、低身長となることがあります。
SGA性低身長の場合、成長ホルモンの分泌が不足しているケースもあるため、ホルモン補充療法を行う場合があります。
骨や軟骨の異常
骨や軟骨の形成異常は、骨格の成長を阻害し、低身長につながる場合があります。
代表的な疾患としては以下のとおりです。
- 軟骨無形成症:最も頻度の高い骨系統疾患の一つで、四肢が短く、胴体が比較的長い体型が特徴
- 軟骨低形成症:軟骨無形成症よりも軽度の症状を示すことが多く、診断が難しい場合もある
- ムコ多糖症:ムコ多糖と呼ばれる物質が体内に蓄積することで、骨や軟骨の成長に影響を及ぼす疾患
骨系統疾患が疑われる場合は、X線検査や遺伝子検査にて、確定診断を行います。治療法は疾患によって異なりますが、成長ホルモン療法が有効な場合もあります。
主要臓器の病気
心臓、腎臓、肺などの主要臓器の病気が、成長を妨げ、低身長となるケースもあります。
具体的な疾患としては、先天性心疾患、慢性腎不全、慢性肺疾患などです。
先天性心疾患は、心臓の構造に異常がある状態で、重症の場合には、全身への酸素供給が不足し、成長に影響が出ることがあります。
慢性腎不全は、腎臓の機能が低下した状態で、老廃物の排出がうまくいかず、食欲不振や貧血などを引き起こし、成長を阻害することがあります。
慢性肺疾患も、呼吸機能の低下により、酸素供給が不足し、成長に影響を及ぼす可能性があります。
慢性疾患がある場合は、その病気の治療を優先的に行うことが重要です。病状が安定すれば、成長も改善することが期待できます。また、必要に応じて、成長ホルモン療法などの治療を検討することもあります。
心理社会的な原因
虐待や育児放棄など、心理社会的な要因が、子どもの成長ホルモンの分泌に影響を与え、低身長を引き起こす可能性があります。
心理社会的な原因が疑われる場合は、専門機関への相談や適切なケアが必要です。
身長が伸びないときの治療方法

身長の伸び悩みは、お子様の将来に関わる重要な問題です。そこで、身長が伸びないときの治療方法について解説します。
東京神田整形外科クリニックでは、体質性低身長(病気ではない)や、身長は低くないけどもっと伸ばしたい方に向けて、専門的な身長治療を行っています。
お子様の身長でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
成長ホルモンの投与
成長ホルモンの投与は、身長の伸びを促進する治療法です。
病気ではないものの身長が低い「体質性低身長」のお子様などに対しても、自費診療で治療可能です。
具体的な治療内容は以下を参照ください。
|
項目 |
内容 |
|---|---|
|
方法 |
ご自宅で毎日1回、寝る前などに専用のペン型注入器を使用し、患者さん自身または保護者が皮下注射を行う。針が細く、痛みは最小限に抑えられている。 |
|
対象年齢 |
骨端線が閉じる前に治療が必要。目安として、男の子は5歳〜14歳0ヶ月、女の子は5歳〜13歳0ヶ月(当院の推奨年齢)。 |
|
治療期間 |
効果を実感するには最低1年、推奨2〜5年程度の継続が一般的。 |
|
費用 |
自費診療の場合、体重によって変動。当院では年間約100万〜500万円程度が目安。(例:体重20kgで年間約168万円〜260万円、体重50kgで年間約420万円〜630万円) ※2025年4月現在 |
体質性低身長のお子さんに対して、長期的に成長ホルモン治療を行う場合の、効果と安全性は、YouTubeでも解説している2005年に発表された論文により証明されています。
この論文では、7年間の追跡調査を行い、47,226人の患者データを分析しています。効果については以下の通りです。
- 成長ホルモン治療は、身長を伸ばす効果が期待できる。
- 特に治療を始めてから最初の1年間で、最も身長が伸びやすく、数センチ程度の伸びが見込める。
- 2年目以降も身長は伸び続けますが、1年あたりの伸び幅は少しずつ緩やかになる傾向。
- 治療を長く続けることで、より高い身長を目指せる。例えば、3年間治療を続けた場合に、元の身長によっては合計で約9cm伸びたというデータもある。
安全性については以下の通りです。
- この研究(最長7年間)では、成長ホルモン治療が原因となるような重い副作用は報告されなかった。
- 治療を受けたお子さんと、受けていないお子さんを比べても、特定の病気(がんや糖尿病など)にかかりやすくなるという証拠は見つからなかった。
栄養補充療法
身長の成長には、バランスの取れた食事が不可欠です。
特に、鉄、亜鉛、ビタミンDなどは、身長を伸ばすために重要な栄養素です。これらの栄養素が不足すると、身長の伸びが阻害される可能性があります。
ビタミンDの重要性について、2022年に発表された熊本大学の研究を参考に解説します。
この研究では、3624人の子どもを対象に、ビタミンDの血中濃度と身長の関係性を調査しました。
結果、ビタミンDが不足している子どもは、そうでない子どもに比べて年間の身長の伸びが低いことが明らかになりました。
具体的には、ビタミンDが十分な子どもは年間約8cm伸びていたのに対し、不足している子どもは約7.4cmしか伸びていませんでした。
これは一見小さな差に見えますが、長期間にわたると大きな差となって現れます。
また、ビタミンDの血中濃度が低い子どもは、屋外で遊ぶ時間が短い傾向がありました。特に冬場は屋外活動が減るため、ビタミンD不足に陥りやすいことが指摘されています。
東京神田整形外科クリニックでは、血液検査で栄養状態を正確に把握し、個別に最適な栄養指導やサプリメントの処方を行います。
ビタミンDは、食事から摂取することもできますが、日光を浴びることで体内で生成することも可能です。
院長自身がYouTubeチャンネル「身長先生」でビタミンDと身長の関係性について解説しています。さらに詳しく知りたい方は、ぜひ動画をご視聴ください。
1歳児の身長が伸びないときによくある質問
お子様の成長は、保護者にとって大きな関心事の一つです。
特に1歳児頃は、発達のスピードに個人差が大きく、他の子どもと比べて身長が低いように感じたり、体重ばかりが増えているように感じたりして不安になることもあるでしょう。
ここでは、1歳児の身長が伸びないことに関するよくある質問と、その回答を詳しく解説します。
1歳で身長が伸びないのに体重が増えるのはなぜですか?
1歳児は成長のスピードに個人差が大きい時期で、身長の伸びと体重の増加に差が出ることがあります。
1歳以降は、0歳から1歳頃よりも身長の伸び率が緩やかになる一方、体重の増加は比較的安定していることが多いです。
1歳児の体重増加は、年間約2kg程度が平均的です。身長がすぐに伸びなくても、それは体が成長の準備をしている期間である可能性があります。
バランスの取れた食事と十分な睡眠を確保することで、後から身長が伸びることもあります。必要以上に心配せず、お子様のペースを見守りましょう。
1歳児の身長は1ヶ月でどのくらい伸びますか?
1歳児の場合、年間で約7〜10cmの成長が目安です。1ヶ月あたりに換算すると、約0.6〜0.8cm程度の伸びが期待されます。
ただし、これはあくまでも平均値であり、個人差があることは意識しておきましょう。
また、月齢によっても成長速度は変化します。1ヶ月でそれほど身長が伸びなくても、年間で見れば順調に成長している場合もあります。
焦らず、長い目で成長を見守ることが大切です。
まとめ
1歳児の平均身長、成長の特徴、身長を伸ばすための生活習慣、低身長の判断基準と原因、治療方法、よくある質問などについて解説しました。
1歳児の身長は、月齢や性別によって異なり、個人差も大きいです。平均身長を参考にしながら、お子様の成長を見守ってあげてください。
・両親の身長が低く、子どもの発育に不安がある
・身長を伸ばしたいが適切なサポート方法を知りたい
・他の医院では、「特に治療の必要はありません」と断られた
東京神田整形外科クリニックの小児身長治療ならば、将来160センチまで成長する予定のお子さんが、しっかり治療を受ければ最大で+10センチぐらいの身長を目指せます。
5〜15歳のお子さんを対象に治療を提供しておりますので、身長について悩まれるときは、ぜひご検討ください。
また、身長先生がお子さんの将来の身長を予測する「身長先生の身長診断」も完全予約制でご用意しています。お子さんの身長を伸ばしていきたいと考えるときは、ご確認ください。
監修者

院長 (全日出勤)
田邊 雄 (たなべ ゆう)
経歴
2011年 金沢医科大学卒業
2018年 日本整形外科学会認定整形外科専門医取得
2018年 順天堂大学博士号取得
2020年 東京神田整形外科クリニック開業

再生医療リードドクター (毎週月曜日、第1・3・5土曜日勤務)
横田 直正 (よこた なおまさ)
経歴
平成11年3月 国立浜松医科大学医学部卒業
平成11年4月~平成18年12月 東京大学医学部整形外科在籍
平成11年5月~平成11年12月 東京大学医学部付属病院整形外科
平成12年1月~平成12年6月 東京逓信病院麻酔科
平成12年7月~平成13年6月 三楽病院整形外科
平成13年7月~平成14年12月 都立広尾病院整形外科
平成15年1月~平成16年6月 東芝林間病院整形外科
平成16年7月~平成17年9月 多摩北部医療センター整形外科
平成17年10月~平成18年9月 都立墨東病院リウマチ膠原病科
平成18年10月~平成19年12月 東京逓信病院整形外科
平成19年7月~平成27年2月 太秦病院整形外科リウマチ科
平成27年3月~平成29年3月 富士見病院整形外科
平成28年6月~平成29年3月 東京ひざ関節症クリニック銀座(院長)
平成29年4月~令和3年4月 東京ひざ関節症クリニック新宿(院長)
令和3年5月~ 総合クリニックドクターランド、新山手病院など

医師 (水曜日勤務)
斎藤 吉由 (さいとう よしゆき)
経歴
1989年 久留米大学 医学部卒業
1990-2000年 久留米大学整形外科医局
2000年-
クリニックヨコヤマ 副院長
泉ガーデンクリニック 整形外科医長
東京ミッドタウンクリニック 整形外科部長
医療法人財団 百葉の会 銀座医院 副院長 等を歴任