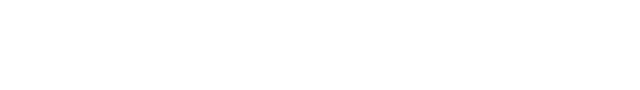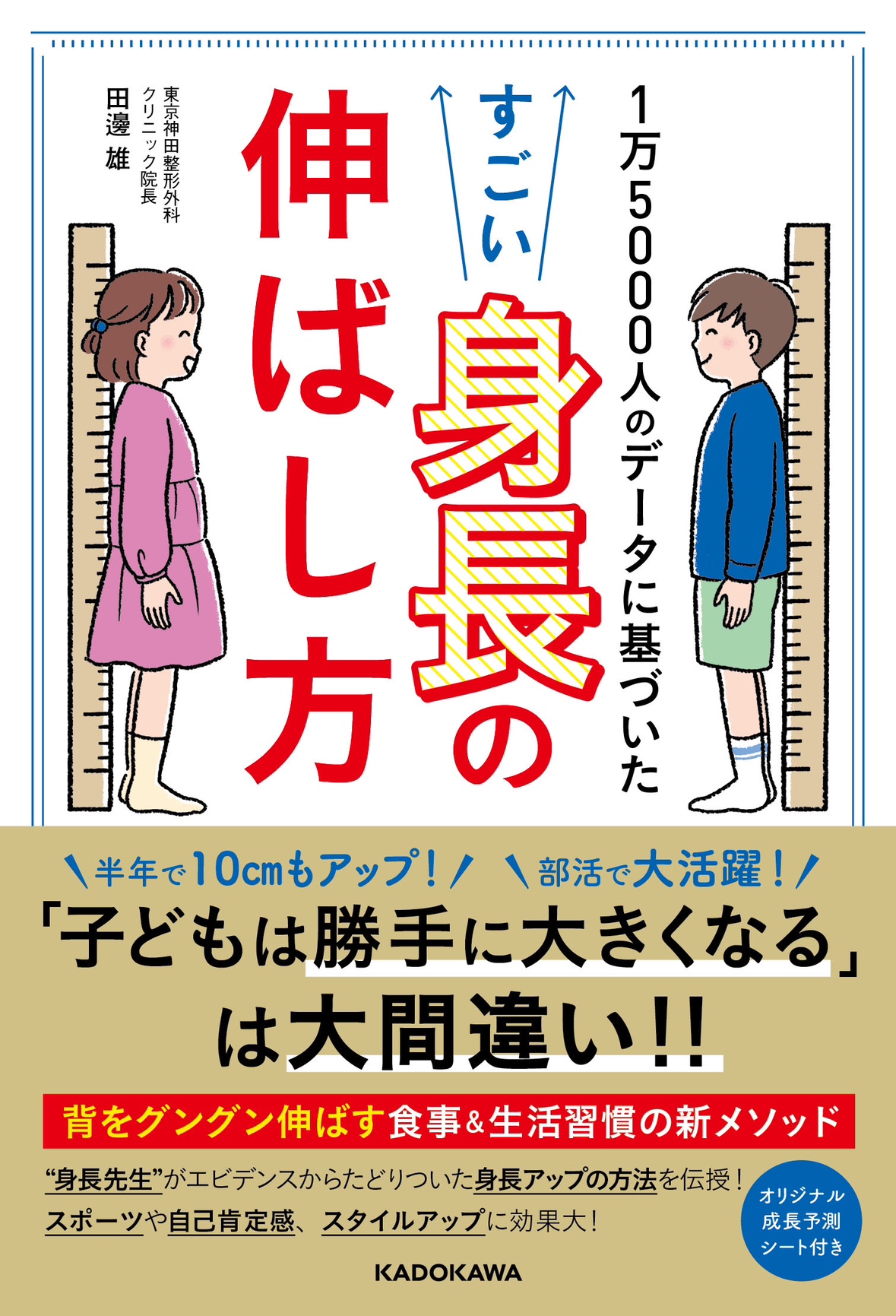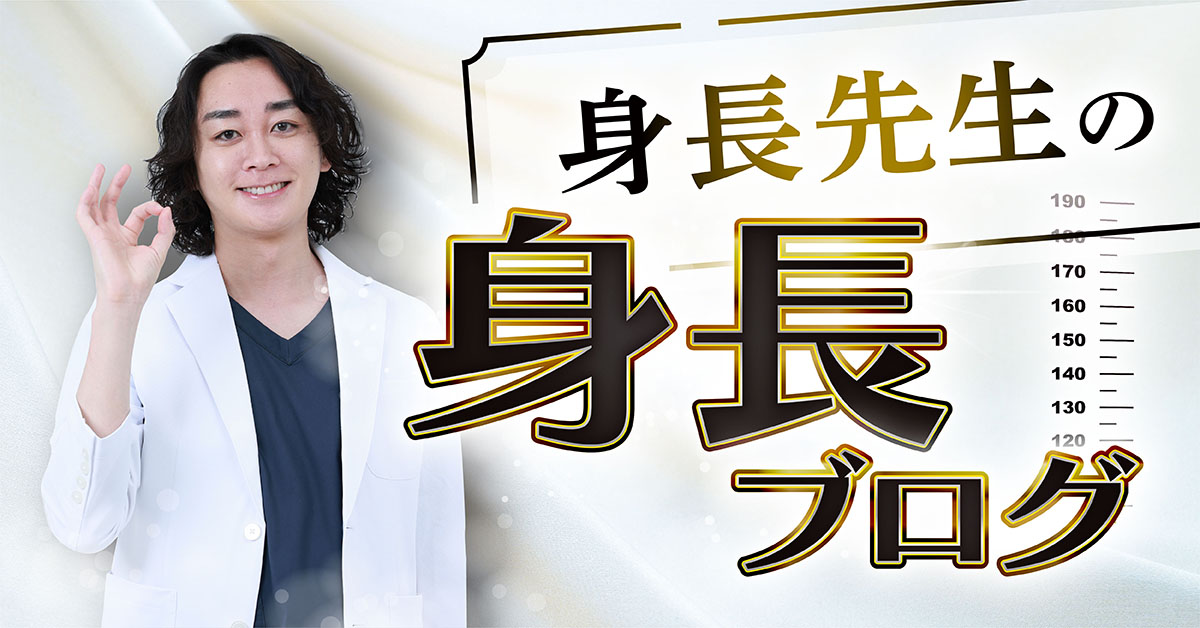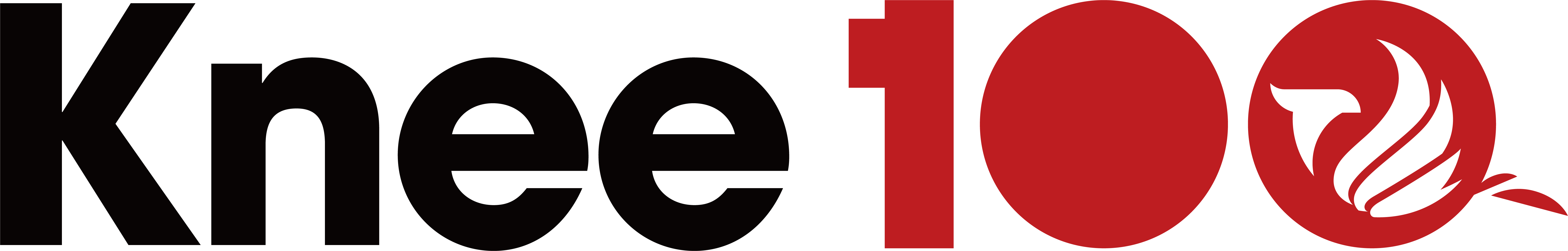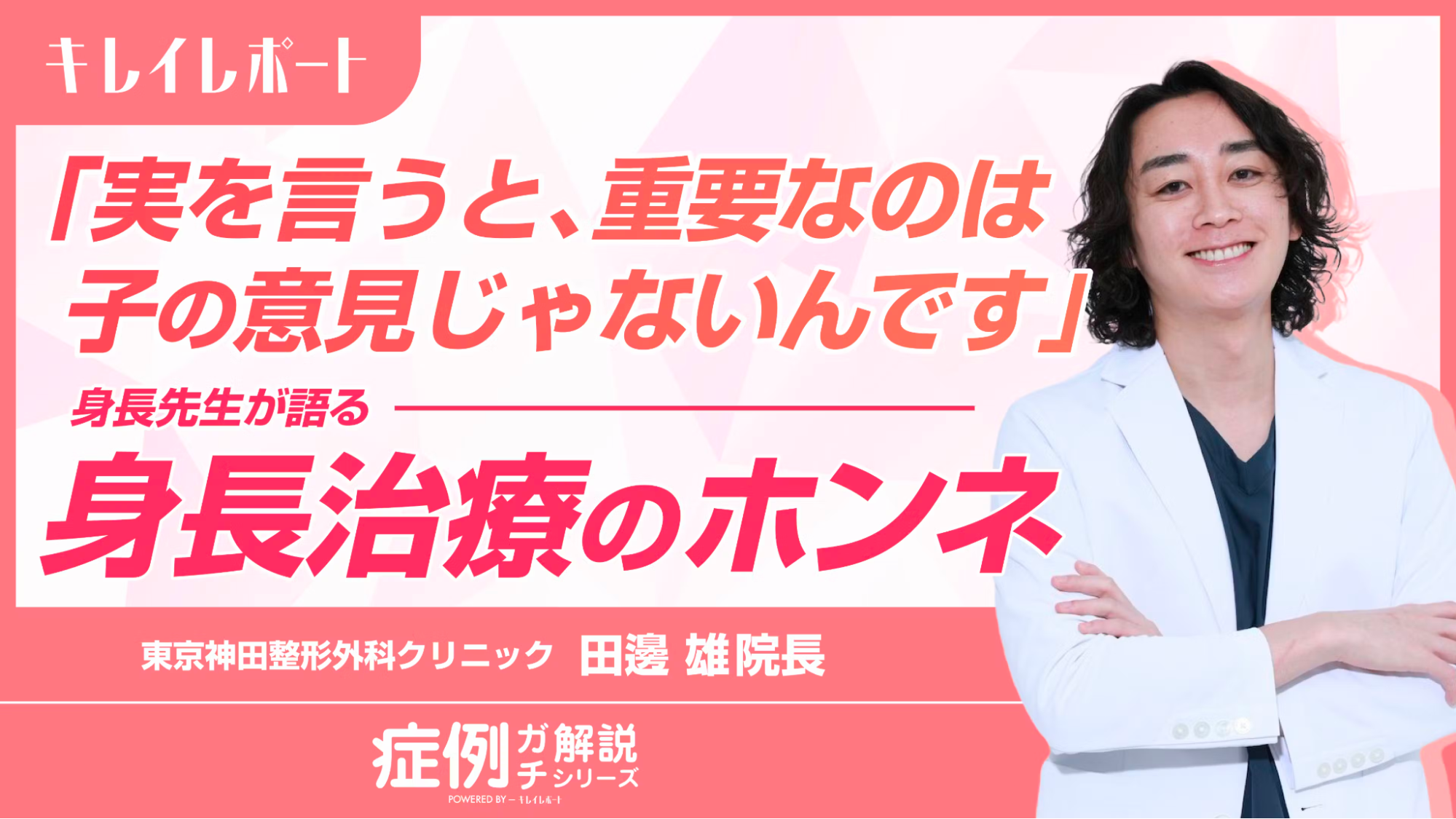五十肩と四十肩の違いとは?由来や対策などを詳しく解説!
東京神田整形外科クリニック、五十肩リハビリ治療責任者・理学療法士主任の石山こと石Pです。
五十肩と四十肩の違いって何?というのをよく聞かれるのですが、皆さん気になりますよね。
なんと、調べてみたらとても恐ろしい事が分かりました。
数年後の五十肩は、もっと若い人が発症しているという可能性が高いです。
ではどうするか?
その対策や由来も含めてご紹介していきます。
五十肩と四十肩の違いは?
五十肩は50代前後に起こる肩の痛みや、関節可動域の制限をまとめたものだと普段からお伝えしています。
四十肩も年代が違うだけで、意味は同じなんですよといつも伝えています。
ではなぜ四十肩・五十肩という2つの言い方があるのかという事ですね。
五十肩は以前にもお伝えした記事がありますので、ご覧ください。
簡単に言いますと、江戸時代の今でいう広辞苑的な書物に「五十肩」という記載がありました。
これが国内の最古の記載になるので、起源は江戸時代になります。
ということは、四十肩の方が後発になります。
本来50代前後で起きていたものが江戸時代から現代までの間に、おそらくどこかのお医者さんが診察していました。
そういう時にですね、五十肩の患者さんを診ていて「40代でも五十肩と同じような症状の方が多いのではないか?これだけ患者さんが多いならむしろ40代のそういった症状を持つ方は、四十肩と呼んだ方がいいのではないか?」という風になっていったのではないかと考えられます。
四十肩の由来というのがはっきりとは分かりませんでしたが、おそらくはこんな感じでできた言葉であると考えられます。
ここで考えなければいけないのは、江戸時代よりも発症が低年齢化している、そういった意味で五十肩の後に四十肩という言葉ができたんですね。
普通に考えたら、様々な面で江戸時代よりも現代の方が富んでいると言えます。
貧しくてご飯が食べられない方は、現代の日本ではまずいません。
栄養状態はそういった意味では、江戸時代よりも現代の方が大幅に改善しています。
この辺りは当院の院長である身長先生が専門ですが、江戸時代の成人男性の平均身長は大体157cmくらいです。
それに比べて現代の成人男性の平均身長は、大体170cmくらいと言われています。
13cmも伸びていますね。
栄養状態が改善したことで身長が伸びたと言えると思います。
ではなぜ栄養状態が改善しているにも関わらず、五十肩というのは低年齢化してしまっているのか。
それを考えた時に、40代・50代の人って何をしているのかと思ったのですが、多分江戸時代も現代も変わらないのは働き盛りであるという事ですね。
ということで、今と昔で働き方に変化がないか調べてみました。
歴史を振り返ってみると、江戸時代のほとんどは一次産業でした。
一次産業というのは農業・林業・漁業と呼ばれるものです。
主に自分の身体を動かして仕事をしていたわけですね。
明治・大正・昭和初期、それ以降は一次産業の他に二次産業も非常に進んできました。
二次産業は一次産業で採れたものを使った産業です。
工業・建築・製造業などですね。
こちらもやはり一次産業と同じように身体を使って仕事をするわけです。
転機は1970年代後半になります。
とうとう三次産業が過半数を上回ります。
三次産業は二次産業以外の産業で、金融・保険・公務なども入ってきます。
先程と異なるのは、デスクワークが中心になってくる事ですね。
さらに2008年では一次産業の国内総生産比率が、たったの2%しかありません。
そして二次産業は約28%、三次産業は残りの約70%と言われています。
ちょっとだけ社会の勉強になってしまいましたが、五十肩の方に戻りましょう。
五十肩の若年化の背景
五十肩の診療ガイドラインの中に、危険因子にデスクワークが挙げられています。
(村木 肩関節周囲炎診療ガイドライン 理学療法 第43巻1号67-72 2016)
これも以前の記事で紹介していますので、参考にしてみてください。
この中では肩にかかる力学的な負荷というよりは、運動不足に起因したものが多くみられると書いてあります。
つまり、これらを順に追って推理してみました。
①江戸時代は一次産業中心で身体をよく動かしていたので、大体50歳前後で五十肩を発症していた。
運動不足よりも加齢による要素が強いと考えられます。
②産業の変化により1970年代以降働き方が変容し、デスクワークに従事する人の割合が非常に増えました。
そして身体を動かす機会が減りました。
③これらの変化によって運動不足となり、40代前後でも五十肩と同様の症状を発症するケースが増えてきたと考えられます。
本来加齢によって発症する年齢よりも若いのですが、昔より運動不足になりすぎたという事が強く要素として現れていると考えられます。
恐らく1970年代から80年代にかけて、四十肩と言われる患者さんが急激に増えて一般用語になったのでは?というのが様々な資料や時代背景から見た私の結論です。
これは私見もありますので、有識者の方でもっと詳しい事が分かる方がいらっしゃいましたら、是非コメントをお願いします。
これから懸念されること
さらに未来の話を仮定でしてみましょう。
2010年代以降はIoTやAIが台頭してきました。
現代の三次産業は益々自動化して、四次産業とも呼ばれています。
またコロナをきっかけにテレワークも増えて、運動する機会が益々減っていると考えられます。
ちなみに1日の歩数の変化です。
江戸時代は1日15000歩くらい歩いていたと言われていますが、現代では大体7000歩くらいしか歩いていません。
さらに緊急事態宣言があると、1日あたり1000歩減るというデータもありました。
ということは、ここからがとても怖いこと。
このままいくと数十年後には、運動不足が加速化します。
それによって四十肩と呼ばれるものは、さらに低年齢化する可能性があります。
その時は三十肩と呼ばれる未来もあり得るわけです。
どういった対策が必要か
ではどうするか。
これはやはり日頃の運動しかありません。
運動不足がきっかけになっているなら、運動でしっかりとカバーする。
「三十肩が当たり前」なんていう時代が絶対に来ないようにするために、私はこれからも尽力していきます。
デスクワークやテレワーク向けの記事も多数ありますので、ぜひそちらもご覧いただき、一緒に治していきましょう。
実際に効果があった方や、ご質問でも結構です。
なんでもコメントをお待ちしております。
また周りに同じような悩みをお持ちの方がたくさんいると思います。
そのときには、こちらの記事を紹介してください。
このブログが広まるほど五十肩で悩む患者さんは絶対に減っていく、本気でそう思っています!
まとめ
以上、五十肩・四十肩で何が違うの?についてでした。
引き続き五十肩について発信していきますので、記事のチェックをお願いいたします。
五十肩専門YouTubeチャンネルではすでに数多くの動画をアップしていますので、チャンネル登録や高評価などよろしくお願いいたします。
実際に五十肩リハビリを行ってみたい方は、ぜひ理学療法士の石山こと石Pをご指名ください!
以上、理学療法士の石Pでした!